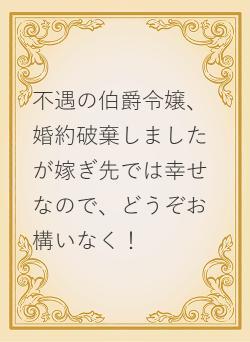そうして裏口から出て家に向かって歩き出してすぐ、私は腕を引かれて驚きつつ、振り向いてさらに驚いた。
「夏乃ちゃん、お疲れ様。ちょっと一緒に来て?」
聞き方は疑問形なのに、その瞳には有無を言わせぬ力がこもっていたので、私は仕方なし高峰さんに連れられて店内のホールに入る。
そこには高峰さんと一緒に来た男女が席で落ち着きなさげにしていて、私たちに気づくと少しホッとしたような表情になってなんだか腑に落ちなくって私は内心で首を傾げるのだった。
「初めまして、高峰くんのお見合い相手なんですってね! もし、なにか誤解してたら大変なので自己紹介させてください。私は三木貴子。大学時代から高峰くんと隣の夫とは仲良くしていたの。今は高峰くんと夫の秘書を兼任しています」
「突然来てごめんね。俺は三木隆で貴子とは夫婦だよ。潤也とは高校からの腐れ縁で、一緒に会社を始めたから副社長なんだ。なかなか結婚も彼女も作る気無かった潤也がお見合いしたって言うから、つい好奇心でついてきちゃって、ご迷惑お掛けしました」
ペコッと頭を下げる男女の左手薬指にはお揃いの指輪が光っている。
どうやら、本当にご夫婦みたいだ。そうか、学生時代からの仲だからこんなに雰囲気が砕けていたのか。
そんな説明から見ていた三人のやり取りに私は、胸の痛みとモヤモヤが消え去ってスッキリしたことに気づいた。
「昨日の出張も実は俺も同行していて、俺が席外してるうちに撮った写メを送ったらしくって、確認すると貴子と潤也で写ってるだろう?なにか誤解してたらと思って来たんだ。やっと、君と親しくなってきて潤也も嬉しそうだし仕事効率も上がってるから、今後とも潤也をよろしくお願いします」
二人はそろって下げてた顔を上げると微笑みあって、その後私にニコリと微笑んでくれた。
「こんなに可愛い子が相手だなんて、幸せものね。高峰くん」
そんなふうに貴子さんがいえば、隆さんもにこやかに言う。
「とにかくもう他所からの縁談攻撃が減るように早く結婚してくれると俺は嬉しいよ。老後の心配も無くなるしな」
そう、言われて、潤也さんはしかめっ面だ。
「別に、お前らに心配されるいわれはないだろう……」
そんなちょっと珍しい態度の高峰さんに、私はなんだか面白くなってきて思わず表情が緩んでしまった。