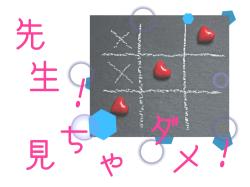彼がどんな意図を持っていたとしても、私が彼のおかげで助かったこと、それは変わりない。
だから、彼が私を助ける意図がなかったことなんてどうでもよかったし、関係なかった。
彼があの場に遭遇してくれたこと自体がもう、私にとっては奇跡でしかないんだ。
「前から目障りだったんだよ、アイツらが。それを追い出すチャンスだっただけ。それでもお前は俺に感謝するのかよ」
「当たり前です」
他人に“その感情は間違ってる”と言われても、私がこの気持ちを覆すことはないだろう。
「変わってんな、お前」
「そうでしょうか」
「……着いてくれば。頬、手当てしてやる」
そう言われて気付いたのは、さっき男に殴られた頬っぺたで。
ぜんぜん気付いてなかったけど、覚悟していた以上に腫れているのが、鏡がなくてもわかった。
不思議なことに、さっきまでは気がつかないくらい何ともなかったのに、腫れていることを知ってしまうと急に痛みがやって来る。
「……あの人たちと同類なんかじゃないです」