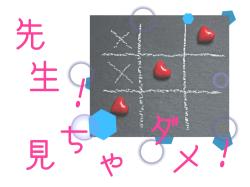*
「紗菜ー!」
どこまでも元気なその声に、私はまた頭を痛めた。この声の主は葵衣。
ほんの少し、ほんの少しだけ吐き気がしてしまい、そんな自分も嫌いになる。
だけど、そんなことを目の前の彼女に知られるわけにはいかなくて、私はいつものように“優しい紗菜”の顔をした。
「……どうしたの、今度は」
「えっへへー!わかるー?」
「だから早く用件を言って」
少しキツい口調になりそうなのを誤魔化すように、私は軽く笑いながら言う。
それがさらに自分の首を締めていることはわかってるけど、長年の癖を今さら直すことなんてできない。
「紗菜に教えてもらったおかげで、小テスト95点取れた!」
「え!?……すごいじゃん。おめでとう。頑張ってたもんね」
彼女の口から告げられた内容は、素直に嬉しかった。
それと同時に、彼女は純粋に私に喜びを伝えようとしてきてくれていたのに、ひどく警戒していた自分が恥ずかしかった。
……でも、大分ひいたとはいえ、朝から私の赤い頬に気付く素振りはなかった。きっと彼女にとって私は、その程度。