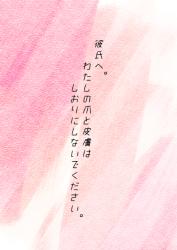「高野くん……」
忘れよう、という弱い心が、ぐっと掴まれたような感覚だ。チェーンのネックレスをぎゅっと握りしめる。
てのひらにくい込んで、ちょっぴり痛かった。チェーンで、彼のことを強く想った心がぎゅっと痛かった。
この痛みが、きっと、高野くんがいた証拠なんだ。
クラスメイトは彼を忘れたふりをして、平常な心を保とうと必死で。そんな彼らに、高野くんはいなかったのではないかと疑う自分が辛くて。
連絡先も、住所も、知らない。話すのも図書委員会の仕事のある時だけ。
証拠なんて、なにひとつなかった。
……だけど。
この、チェーンでだきしめられた弱い心の痛みが、きっと、彼との日々を忘れさせない。絶対にあったと、証明させられる。
ねぇ、高野くん、だいすきです。
今度、逢おうね。いつか、逢おうね。
その時はぎゅっと、
だ き し め て
Fin.