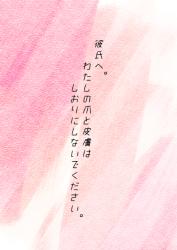私の顔から目をそらさない、彼。むしろ、そらせないのかもしれない。
それは、申し訳なさといえばそうなのかもしれないし、会話を終えたら私がめんどくさい反応をしそうだなという不安からかもしれない。
彼が、くちびるをわずかに開いて、ほんの一瞬閉じて、また開く。
しゃべらなきゃと思いつつ、しゃべらない。しゃべれない。そんな感じ。
ただ単に話題がない、というのとは違いそうだった。
「小林ー!」
先生の怒ったような声が教室に響き渡った、その瞬間。
彼は、救われたようにまばたきをし、少し曲がっていた自分の制服のネクタイを、真っ直ぐにした。
私と話すときよりも、私と話さないで済んだときのほうが……嬉しそう。