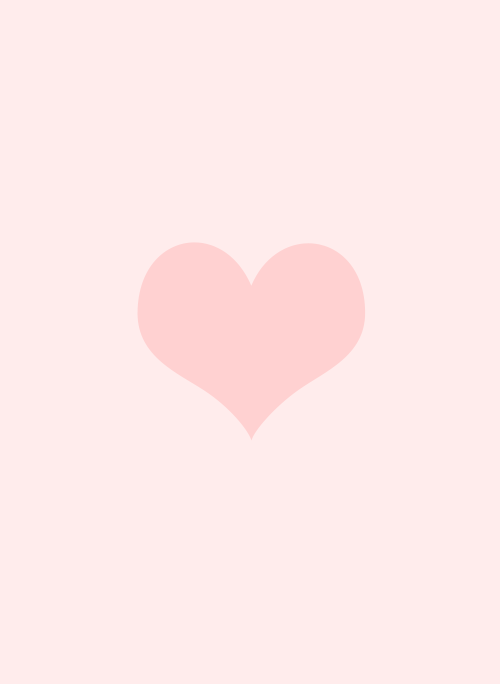「わたしたちのことは気にしないで、行ってきなさい」
「お母さん……」
気づいてたんだ。
わたしが秘密を知ってしまったこと。
わたしと璃汰の関係も。
一体いつから見守っていてくれてたの?
「友達が大変なんだろ?」
「お父さ……っ」
友達。そう、わたしと璃汰は友達なの。
異母姉妹である事実はあれど、“家族”にはなれない。
だけど一番の理解者にはなれる。
「お母さん、お父さん、ありがとう」
2人がそうであるように。
「行ってきます!」
2人の手の甲をぎゅっと握る。
わたしに勇気を、力を、ちょうだい。
真っ白なエプロンをお母さんに託し、肩からずり落ちたお父さんのスカジャンを羽織り直した。
青緑色と白色の大きめな仮面で守られた“かわいい”が、わたしの強み。
スマホをポケットに入れ、家を飛び出した。
「――不思議な運命だな……」
「悲しむよりずっといいわ」
「……ああ、そうだな。璃汰ちゃんを無事に守れるといいな」
「きっと大丈夫よ。信じましょう?」
わたしの背中を見つめながら、お父さんとお母さんは微笑み合う。
温かな想いは確かに、触れていた肩から伝わった。