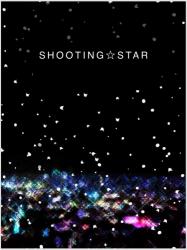「で、結局、例の人には会えたわけ?」
昼休み。
窓枠に座って、弁当を広げながら海都が訊いてくる。
「例の人?」
「あのシュシュの落とし主。」
「ああ、響子さん。会えたよ。」
「えっ!?既に名前で呼ぶ関係?早くね?」
「あれから、なんか平日は毎日のように会うんだよ。」
「え、マジか。」
海都は急に小声になって、踏み台にしていた椅子に座り直した。
そのまま、にゅっと顔を近づけてくる。
「で、どこまでヤったの?」
「どこまでって……お前さぁ。」
「いいじゃん、どこまでだよ?おっぱいは?大きかった?」
大河はその顔を押し返しながら、呆れた声をだす。
「まだ、連絡先も交換してねえよ。」
「はぁーーー!?」
「叫ぶな。」
「だって。」
海都を無視して、弁当を広げる。
叔母さんの作る弁当は簡素だ。
ふりかけのご飯、たっぷりの蒸し野菜、肉のおかず。
今日は唐揚げ……昨日の夕飯の残り物。
それでも、毎日持たせてくれるのを有り難いと思う。
いただきます、と、大河が手を合わせると、海都も手を合わせた。
「で、どんな人なの、その人。」
「響子さん、な。っていうか、質問の順番おかしいだろ?」
「だって、大河、毎日会ってるとか言うから。」
「帰りの駅で遭遇するんだよ。」
「待ち伏せ?」
「待ち伏せも、待ち合わせもしてない。」
「で?」
「駅で会って“おつかれさま”って。路線一緒だから途中まで一緒に電車にのる。」
「うん。」
「それだけ。」
「え?」
「それだけ。」
「マ?」
「昨日は本屋に寄った。駅ナカの。」
「それだけ?」
「それだけ。」
「マ?」
「しつこいよ?」
弁当から顔を上げようともしない大河のウンザリした口調に、海都は笑って、弁当を掻き込む。
大河は箸を置いて、窓の外を眺めた。
数人の教師が校庭に出て何やら集まって話しているのが見える。
「……俺さ、大人って、もっと大人だと思ってたんだけど。」
「うん。」
「響子さんは、なんか自由な感じがする。」
「子供っぽい?」
「子供っぽくはないかな。」
「いくつなの?」
「多分、30くらい。」
「お、思ったよりも歳上。」
「お姉さんいくつだっけ?」
「26。」
「30代の女性って、想像出来る?」
「ピンと来ねえ。」
「響子さんと話しててもピンと来ない。」
「何を話すの?」
「ラーメン屋のTシャツは何故黒いのか?とか。」
「ピンと来ねえ。」
「漫画は雑誌派だとか。」
「お、何読むの?」
「主に少年誌。週刊の。」
「ピンと来ねぇー!」
「だろ?」
響子さんは、話題が多い。なんでもないような話ばかりなのだが、それをとても楽しそうに言葉にする。
でも、それは、思い描いていた大人の女性の会話とは掛け離れていて、彼女の実態は掴めないままだった。
「でも、可愛いんだろ?」
「歳の割に。」
「花柄のシュシュ付けちゃうタイプ。」
「普段は結んでない。」
「そうなの?」
「食事と仕事用だって。」
「へぇ。……あ、前に聞いたことあるんだけど。」
海都は口の端だけでニヤリと笑う。
その笑みは嫌な予感しかしない。
「何?」
「シュシュの趣味は下着の趣味だって。」
「は?」
「だから、黒いレースのシュシュは黒いレースのショーツ、ピンクのサテンはピンクのすべすべしたショーツ。あの人のシュシュは……」
紺地にピンクの大きな花柄。指先の滑るような光沢のある生地。
「おい、やめろよ!」
「……想像した?」
「……しちゃっただろ。」
「大河、顔、赤い。」
「誰のせいだよ。」
「ダイタイ、オレ、ワルイ。」
「なんでカタコトなんだよ。」
「ゴメン、チョウシ、ノッタ。」
両手を合わせて頭を下げる海都の後頭部を掴む。
海都は笑いながら「ごめんて。」と、もう一度呟いた。
「しょーがねぇな。」
海都を解放すると、大河は笑いながら残りの弁当を片付ける。
その話の真偽を確かめる日は、いつか来るのだろうかと、響子さんのことを思う。
昼休み。
窓枠に座って、弁当を広げながら海都が訊いてくる。
「例の人?」
「あのシュシュの落とし主。」
「ああ、響子さん。会えたよ。」
「えっ!?既に名前で呼ぶ関係?早くね?」
「あれから、なんか平日は毎日のように会うんだよ。」
「え、マジか。」
海都は急に小声になって、踏み台にしていた椅子に座り直した。
そのまま、にゅっと顔を近づけてくる。
「で、どこまでヤったの?」
「どこまでって……お前さぁ。」
「いいじゃん、どこまでだよ?おっぱいは?大きかった?」
大河はその顔を押し返しながら、呆れた声をだす。
「まだ、連絡先も交換してねえよ。」
「はぁーーー!?」
「叫ぶな。」
「だって。」
海都を無視して、弁当を広げる。
叔母さんの作る弁当は簡素だ。
ふりかけのご飯、たっぷりの蒸し野菜、肉のおかず。
今日は唐揚げ……昨日の夕飯の残り物。
それでも、毎日持たせてくれるのを有り難いと思う。
いただきます、と、大河が手を合わせると、海都も手を合わせた。
「で、どんな人なの、その人。」
「響子さん、な。っていうか、質問の順番おかしいだろ?」
「だって、大河、毎日会ってるとか言うから。」
「帰りの駅で遭遇するんだよ。」
「待ち伏せ?」
「待ち伏せも、待ち合わせもしてない。」
「で?」
「駅で会って“おつかれさま”って。路線一緒だから途中まで一緒に電車にのる。」
「うん。」
「それだけ。」
「え?」
「それだけ。」
「マ?」
「昨日は本屋に寄った。駅ナカの。」
「それだけ?」
「それだけ。」
「マ?」
「しつこいよ?」
弁当から顔を上げようともしない大河のウンザリした口調に、海都は笑って、弁当を掻き込む。
大河は箸を置いて、窓の外を眺めた。
数人の教師が校庭に出て何やら集まって話しているのが見える。
「……俺さ、大人って、もっと大人だと思ってたんだけど。」
「うん。」
「響子さんは、なんか自由な感じがする。」
「子供っぽい?」
「子供っぽくはないかな。」
「いくつなの?」
「多分、30くらい。」
「お、思ったよりも歳上。」
「お姉さんいくつだっけ?」
「26。」
「30代の女性って、想像出来る?」
「ピンと来ねえ。」
「響子さんと話しててもピンと来ない。」
「何を話すの?」
「ラーメン屋のTシャツは何故黒いのか?とか。」
「ピンと来ねえ。」
「漫画は雑誌派だとか。」
「お、何読むの?」
「主に少年誌。週刊の。」
「ピンと来ねぇー!」
「だろ?」
響子さんは、話題が多い。なんでもないような話ばかりなのだが、それをとても楽しそうに言葉にする。
でも、それは、思い描いていた大人の女性の会話とは掛け離れていて、彼女の実態は掴めないままだった。
「でも、可愛いんだろ?」
「歳の割に。」
「花柄のシュシュ付けちゃうタイプ。」
「普段は結んでない。」
「そうなの?」
「食事と仕事用だって。」
「へぇ。……あ、前に聞いたことあるんだけど。」
海都は口の端だけでニヤリと笑う。
その笑みは嫌な予感しかしない。
「何?」
「シュシュの趣味は下着の趣味だって。」
「は?」
「だから、黒いレースのシュシュは黒いレースのショーツ、ピンクのサテンはピンクのすべすべしたショーツ。あの人のシュシュは……」
紺地にピンクの大きな花柄。指先の滑るような光沢のある生地。
「おい、やめろよ!」
「……想像した?」
「……しちゃっただろ。」
「大河、顔、赤い。」
「誰のせいだよ。」
「ダイタイ、オレ、ワルイ。」
「なんでカタコトなんだよ。」
「ゴメン、チョウシ、ノッタ。」
両手を合わせて頭を下げる海都の後頭部を掴む。
海都は笑いながら「ごめんて。」と、もう一度呟いた。
「しょーがねぇな。」
海都を解放すると、大河は笑いながら残りの弁当を片付ける。
その話の真偽を確かめる日は、いつか来るのだろうかと、響子さんのことを思う。