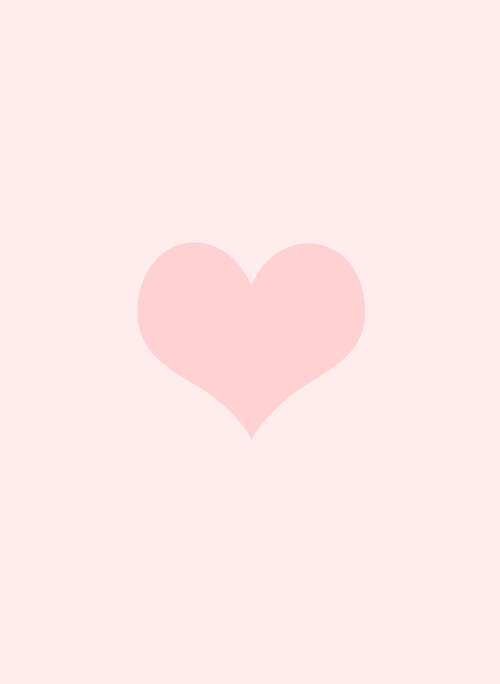緋咲がハンカチを取り出して遠慮なく口を拭っていると、
「あー、お子さまには刺激が強すぎたかな?」
と翔太が笑った。
その視線にさらされても、貴時は無表情のまま立ち尽くしていた。
「おかえり、トッキー。今、将棋の帰り?」
今のやり取りには触れず、緋咲はいつもと変わらない笑顔を貴時に向けた。
貴時は何も答えず、緋咲の乱れた髪の毛に目を向けている。
「将棋?」
反応したのは翔太の方だった。
「そうそう! この子、同じ団地の子なんだけど、ずーっと将棋頑張ってるの。すっごく強いんだよ!」
誇らしげに緋咲は言ったけれど、翔太は鼻で笑って貴時に近づく。
「将棋もいいけど、男ならサッカーやれ、サッカー。その方が絶対モテるから」
緋咲の眉間に皺が寄る。
怒鳴らなかったのは、若干ながら残っている恋心が邪魔したせいだ。
モテたいがためにサッカーをやり、事実その成果を出している翔太にとっては、絶対的真理なのだろう。
貴時の頭を翔太の大きな手がポンポンと叩く。
その瞬間、それまでピクリとも動かなかった貴時が、思い切りその手を払った。
「ぼくは将棋がいい」
貴時の目に、翔太などは映っていない。
誰に何を言われても、貴時が信じたひとは別にいる。
大切に持っていたはずのルーズリーフは握り潰され、手の中でしわしわになっていた。
「将棋があればいい」
「へえ」
振り払われた手で翔太はふたたび強く貴時の髪を乱し、言葉を失う緋咲に近づく。
「じゃ、緋咲。また明日」
ミルクチョコレート色のセミロングにもう一度キスをして、翔太はニヤリと笑って帰って行った。
『緋咲』
翔太に言われたどの言葉より、その呼び声が耳に残って、今は「ひーちゃん」と呼び掛けることはできそうにもない。
余韻を消し去るように緋咲は髪の毛を払い、貴時と目線を合わせる。
「トッキー、ごめんね」
貴時は黙って首を横に振る。
悪いのは緋咲ではないのに、なぜそんな顔をするのか。
それすら腹立たしかった。
「私はずっとずーっと応援してるからね」
緋咲が乱れた髪の毛を直すように、貴時の頭を撫でる。
生まれて初めて、その手を振り払いたいと思った。
『小学生名人戦で準決勝まで残った!』
一番伝えたいひとに、一番伝えたいことは、とうとう言えなかった。
「あー、お子さまには刺激が強すぎたかな?」
と翔太が笑った。
その視線にさらされても、貴時は無表情のまま立ち尽くしていた。
「おかえり、トッキー。今、将棋の帰り?」
今のやり取りには触れず、緋咲はいつもと変わらない笑顔を貴時に向けた。
貴時は何も答えず、緋咲の乱れた髪の毛に目を向けている。
「将棋?」
反応したのは翔太の方だった。
「そうそう! この子、同じ団地の子なんだけど、ずーっと将棋頑張ってるの。すっごく強いんだよ!」
誇らしげに緋咲は言ったけれど、翔太は鼻で笑って貴時に近づく。
「将棋もいいけど、男ならサッカーやれ、サッカー。その方が絶対モテるから」
緋咲の眉間に皺が寄る。
怒鳴らなかったのは、若干ながら残っている恋心が邪魔したせいだ。
モテたいがためにサッカーをやり、事実その成果を出している翔太にとっては、絶対的真理なのだろう。
貴時の頭を翔太の大きな手がポンポンと叩く。
その瞬間、それまでピクリとも動かなかった貴時が、思い切りその手を払った。
「ぼくは将棋がいい」
貴時の目に、翔太などは映っていない。
誰に何を言われても、貴時が信じたひとは別にいる。
大切に持っていたはずのルーズリーフは握り潰され、手の中でしわしわになっていた。
「将棋があればいい」
「へえ」
振り払われた手で翔太はふたたび強く貴時の髪を乱し、言葉を失う緋咲に近づく。
「じゃ、緋咲。また明日」
ミルクチョコレート色のセミロングにもう一度キスをして、翔太はニヤリと笑って帰って行った。
『緋咲』
翔太に言われたどの言葉より、その呼び声が耳に残って、今は「ひーちゃん」と呼び掛けることはできそうにもない。
余韻を消し去るように緋咲は髪の毛を払い、貴時と目線を合わせる。
「トッキー、ごめんね」
貴時は黙って首を横に振る。
悪いのは緋咲ではないのに、なぜそんな顔をするのか。
それすら腹立たしかった。
「私はずっとずーっと応援してるからね」
緋咲が乱れた髪の毛を直すように、貴時の頭を撫でる。
生まれて初めて、その手を振り払いたいと思った。
『小学生名人戦で準決勝まで残った!』
一番伝えたいひとに、一番伝えたいことは、とうとう言えなかった。