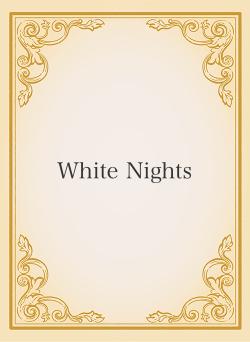棗と私の、並々ならぬ覚悟と恐怖心
それらが複雑に混ざり合う空間。
なんとも居心地の悪い其処で、棗はゆっくりと話し始めた。
「迎えに来たんだ」
「…は?」
「俺はお前を迎えに来た」
「棗、」
「帰ろう?セリナ」
「ちょっと待ってよ棗」
「皆待ってる」
「自分が何言ってるのか、分かってる?」
私で私の耳を疑った。
なんて?
棗は今、
…なんて言った?
『迎えに来た』?
誰を?誰が?
「あの日、お前の手を取らなかった。背中をただ見送った俺達のこと。
許してくれなんて言わない」
「なつ、め」
「ただ俺には、上二人の真意が分からなかった。お前がどこにいるのか。お前がちゃんと生きているのか。お前がどうして戻ってこないのか」
───二人は知ってたみたいだったけど。
そう付け足した棗に、私の頭はショート寸前。
「…」
「かと言って何も言わないあの人らを責める訳にも行かなかった。結局、俺がお前を諦めることが最適解なんだと思ってた」
「…、」
「お前はチームを見限って、俺らは見限られたんだろうな」
「…棗」
「そう思えば筋が通るんだもんな」
「…」
「それに。彼処にお前のこと嫌いな奴なんていないことくらい分かってたし」
「…、」
「…お前は悪くないんだって、皆ちゃんと知ってたよ」
───悪いのは自分たちだったんだ、ってこともな。
苦しそうな棗を見れば、それが私にはもっと苦しくて。
直視していられなかった。
だから眼を逸らせば、棗が無理矢理私の視線を自分に合わせた。
「『あいつに見限られるようなチームなら、とっくに潰れてんだろ』って。
あの人が言ったんだ」
「…っ、」
「芹那は見限ってなんかない」
「…ミオが言ったの?」
「うん。ぶっちゃけあの人が一番苦しそうだったけどな」
「…なにそれ」
「『迎えに行って来い』って。昨日言われた」
────俺も何が何だかわかんなかったけど。
そう言って妖しく口角を上げた棗に、最早私は足が竦む思いだった。
棗の言葉に、私の理解が追いついていかない。
頭の中で、何度も反芻する棗の声。
『芹那は見限ってなんかない』
『迎えに行って来い』
…嘘でしょ。