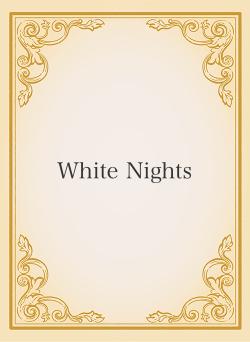友達と言う表現に間違いがないから。
私たちの間でだけは。その表現が正しいから。
だから余計に縛られる。
棗も私も、それは互いに同じこと。
「親友」。
純粋に、私たちだけは
この暗闇に紛れた世界で「親友」を貫いていた。
いや、貫いていたかったという方が正しいのかもしれない。
私は目をそらす。
いとも簡単に。
その甘い誘惑と、切実な思いから。
無自覚ではない。
意図的に。
「…なんか、喉乾いたね」
真っ青な自販機を正面からまじまじと眺める。
暖かい飲み物が欲しいところだけれど、あいにく全て売り切れらしく。
私と棗が選んだのは少し濁ったエナジードリンクだった。
昔、二人でよく飲んだ。
「───棗」
私は、真っ直ぐ棗を見据えて尋ねる。
「会いに来てくれてありがとう」
「…うん」
「でもね」
「…うん?」
「私はこんな形で会いたくなかったな」
「……なんで」
「用件を、教えて」
この返答次第で私はここから逃げる。
こんなにも健気な友達から。
棗はそんな私に一切気づく様子もなく、未だ違和感の残る表情で答えた。
「セリナ」
───逃げないで。今だけちゃんと、聞いて
私はその答えに一瞬目を伏せて、それから棗にもう一度向き直る。