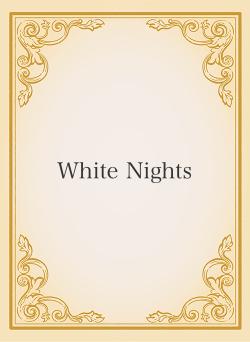だって私にはもう
───『最強』の肩書を、背負う器量はない。
「棗もういい、降ろして」
街灯の薄明かりに照らされたコンクリートの上で、みっともなく足が空を切る。
やり場のない思いと、行き場のない空間。
足をバタバタさせると、何度か棗の太ももに当たるのが分かった。
そのまましばらく歩いて
近くの公園の湿ったベンチに、棗はようやく私を下ろした。
「…………セリナ、っ」
当然、息を着く間もなく、またすぐに体を拘束される。
…分かってる。
彼等も、私をずっと捜してくれていたはず。
彼等から、逃げ続けた私を。
「…棗、」
逃がさないと、棗の濡れた目が物語っていた。
「…大丈夫。棗を目の前にして、もう逃げたりしない」
はるばる、私に会いに来てくれたんでしょう?
それは嘘偽りなく、嬉しいことだから。
「…ほんとか?」
「うん」
「でも前はそう言って逃げた」
「…うん」
「信じて待っても、どうせお前は帰ってこない」
「よく分かってんじゃん」
「もうそれは分かった」
「…そう」
「俺らが『狼』で待ってたってお前は来ないんだろう?」
「…そうだね」
「…お前は、ほんっとに何もわかってない」
「…え?」
「俺は、俺はチームとかそんなのどうでもいい」
「……棗、」
「せめて俺とだけは、」
「…ごめん、棗」
「一人の友達として会いに来て欲しかった」
「…うん」
「俺とはそれが叶ったはずだろ、馬鹿…っ」
棗はそう言って、
ひどく歪んだ表情で私の瞳を真っ直ぐに見つめる。
どうしても逸らせない視線の中で
少し冷えた夜の空気がまた一つ、頬を貫いていく。