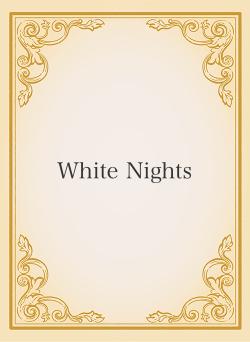「───やっと見つけた」
じわり、私の目尻にも涙が滲む。
少し男声にしては高い
上ずった声の主、───山崎 棗。
彼は厄介なことに、
私が今この地球上で一番会いたい、一番会っちゃいけない人物だった。
───六代目「狼」、親衛隊長。
小さな体に大きな肩書を背負った、若干16歳の少年である。
「───セリナ、」
「棗…?」
「やっと会えた…っ」
「…棗」
私を熱く抱擁する棗。
その声は何度も何度も、切実に私の名前を呼ぶ。
「セリナ、セリナ、っ、セリ、ナ」
「…うん。久しぶり、棗」
それはまるで、ここにいる私の存在を確かめるかのようで。
私の首を締め付ける両腕は、悲しいほどに温かい。
「セリナ…っ」
「うん」
───ここにいるよ
いつの間にか、雨が止んでいた。
棗の髪と、私の髪から滴り落ちる水の音。
それ以外何も、耳に入ってこなかった。
それから何分がたったか。
とりあえず一旦立とうと、震える足を必死に動かす。
「腰抜けた?」
「……もうちょっと休んで良い?」
棗が力なく笑った。
───嗚呼、何かな。
弱くなったな、死にかけたごときで。
ガクガクと、みっともないくらいに膝が笑っている。
震えは全身に広がって
私は棗にされるがまま、その腕に抱かれた。
「ちょっ、棗待って」
「歩けないんでしょ」
「恥ずかしいから、」
「黙っておぶられとけ」
そんな自分と棗とを見比べて
ふと思う。
大きくなったなあ、棗。
こんなこと言ったらきっと怒るけど。
棗の背中はいつの間にか、とても頼もしくなっていた。