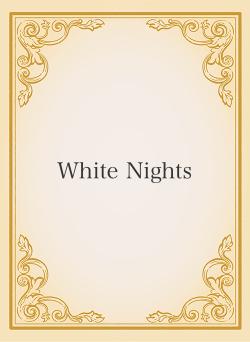あの件における一番の責任はどこからどう見ても私にあって
実は私が、それを一番理解していて。
冷静な瞳の奥を
それでも悲しみに染めていたことに。
「…っ」
その不器用な舌打ちは少し、哀しい。
「わぁーったよ」
しかし、次にそう言った諒二の顔は
先ほどより幾分も少し落ち着いていたようにも思えた。
いつもそうだ。
最終的に折れるのは諒二。
どれだけ私が憎くたって、
どれだけ私が悪くたって
だからといって私のことを蔑ろにしてはくれない。
結局優しい。こいつも。
わがままを言うようだけれど
ずるいよ。
まるで私だけが置いてかれてるみたい。