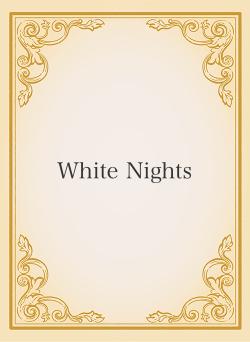どこか遠くへ。
彼等の、棗の眼から逃れるどこかへ。
足には多少の自信があった。
なにより、
走りながら拭う余裕もない涙を隠そうと必死で。
その思いを糧に公園を一つ、はしごした。
隣町の中央公園。
すぐ近くまで迫る棗の気配を感じながら公衆トイレへと逃げ込む。
それでもなんだか落ち着かなくて
よじ登った窓から飛び降り、道路沿いに植えられた植木の影へ。
「…っ、はあっ、はあ、」
───泣きたくて、仕方がなかった。
こうなることは想定内だった。彼等に会ってしまえば。
だから会いたくなかった。
走馬燈のように私の頭を走り抜けるものがある。
『思い出』だったのだ。
いいものも、悪いものも。
あいつらと過ごした日々は、なににも変え難かった。
だから余計、脳が彼等を思い出すことを拒んでいた。