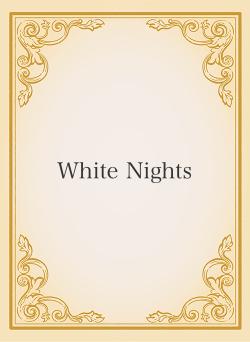少しでも気を緩めてしまば負けだと思った。
零れてしまいそうな想いが。
それが、喉元まで出かかっていたから。
「俺は嫌だ」
伏せていた顔を上げて、棗が私をまっすぐ見つめる。
そして間髪入れずに
「一緒に、帰ろう」
そう言って、手を差し出した。
「、セリナ!」
「…、」
「俺の手、掴んで…」
「…棗」
本心は。
本心はね。
───今すぐに、この手をとって笑いたい。
そしてもう二度と。
離したくない。
心でそんなことを思って、もう一度その手を見つめながら。
「ごめん、棗」
私は表情すら変えずに、重苦しく口を開いた。
「──誰かが、責任を取らなきゃ」
そっと、踵を返す。
背を向けた。
彼等の無垢な想いから、冷たく
目を逸らした。