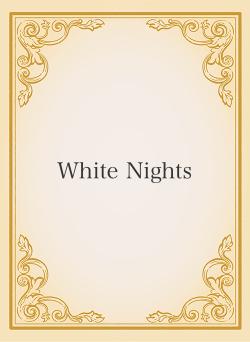けれど。
『正義のヒーロー』
肝心の伊織の目には、そうは映らなかったようだ。
「ーーありがとう。好青年」
あくまで自分を助けた人間に向かい、可愛らしい笑みで吐き捨てるようにそう言って。
もう一度、スマホの画面に目を落とした。
「…あの」
再度大きなショックに見舞われた俺は、情けなく苦笑して、小さく彼女の肩を叩く。
先程までのやり取りを見ていればその行為にすら恐怖を感じた。
…が。
ゆっくりと視線を合わせた彼女は
想像以上に、優しく俺を見つめ返していた。
トクンと心臓が跳ねた気がした。
恥ずかしいほど甘い跳躍だった。
「…なに?」
「連絡先、貰ってくれないかな」
「…誰の?」
「いや、えっと、俺の」
「どうして?」
茶色がかった双眼に射抜かれる。
『どうして?』
あまりにも純粋な問い掛けだった。
だから余計に戸惑って
俺はとんでもないことを口走った。
「付き合いたい」