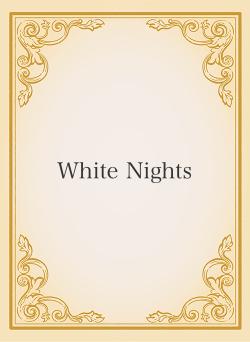桜の木を連想した。
美しく佇む、それでいて大きな桜の木。
そのイメージがピタリとハマった。
きっとあの瞬間、一瞬にして俺は彼女に落ちていた。
「…」
「…」
ーー『セリナ』と呼ばれた金髪の女は、トイレからしばらく戻らなかった。
円堂 芹那。
まさに、“彼女”である。
桃色の彼女、ーー伊織はその間、スマホから目を離さず
ごく一般的に、平穏に、暇を持て余していた。
加えて彼女は、“芹那”が帰ってくるまで
手元の食事に手を付けなかった。
彼女の周りだけが俺には輝いて見えて
しかし、それは無論俺だけに当てはまる話でもなく。
彼女に突き刺さる視線が
一旦、両手では数え切れないことはどう見ても明らかだった。