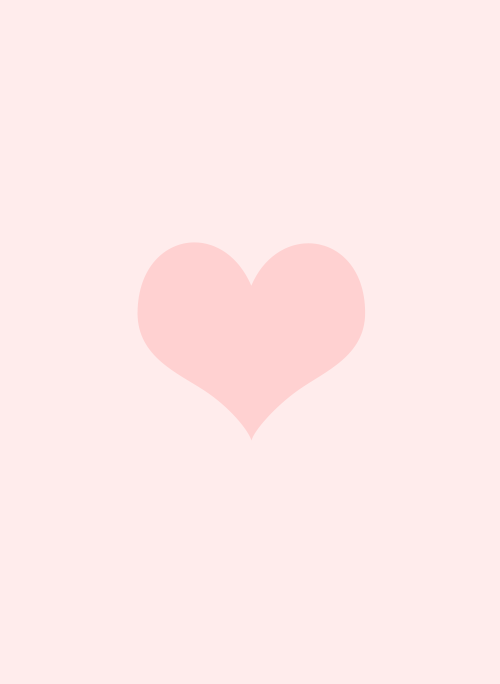スーパーは開いていたけれど、丸一日の停電でかなり廃棄された食品もあったようで、充実したラインナップとは言えなかった。
冷凍食品の棚は空っぽ。
冷蔵や生もの系もかなり少ない。
各家庭でも食料不足に陥っていたのか、少ない商品に需要が殺到したらしい。
お惣菜は空に近く、パンや麺類は残りわずか。
結局思うような買い物はできず、おばさんとも電話で相談した結果、“貝出汁ラーメン”なるものとロールパン、グレープフルーツを買ってホームセンターに移動した。
こちらも電池や大きな懐中電灯、ランタンの類い、カセットコンロなんかも売り切れ。
他に緊急に買うようなものもなく、わたしはタオルやカーテンを眺めながら、レジに向かった啓一郎さんを待った。
「行こうか」
楽しみにしていたのに、あまりにあっけないお出かけの終わり。
がっかりして黙ったまま車に乗り込むわたしに、啓一郎さんは今買ったビニール袋を差し出した。
「あげる」
「わたしに?」
中身はなんてことない小さな白い懐中電灯だった。
わたしの手のひらに収まるほどのそれは安っぽく、機能はごくシンプルなもの。
だからこそまだ少し売れ残っていたらしい。
「ありがとうございます!」
パッケージを開けてみると、小さいながら白っぽくて強い灯りが点灯した。
「これ、上に向けた状態で置ける形状だったから」
啓一郎さんは懐中電灯を天井に向け、その上にボトルホルダーに残っていた空のペットボトルを置いた。
「水の入ったペットボトルをこうして乗せると、乱反射してランタンみたいになるんだって」
今乗せたペットボトルは空で、懐中電灯の明かりはただ通過していっている。
「そうしたら少しは、」
言い淀む啓一郎さんの顔はどんどん朱に染まっていく。
「少しは、シンデレラの舞踏会みたいに、なる、かも」
「……そんな顔するなら、言わなきゃいいのに」
感染するみたいにわたしの顔も熱を持つ。
押し黙った啓一郎さんは少し車の窓を開けた。
走らせると冷たい風が頬を冷ます。
「嘘です。ありがとうございます。今夜試してみましょうね」
カチカチと意味もなく懐中電灯をつけたり消したりした。
嬉しくて嬉しくて。
小さな懐中電灯にペットボトル。
安っぽいシャンデリアでは王子様にもシンデレラにもなれないかもしれないけれど。
でも啓一郎さん。
無理矢理手を取ったら、わたしと踊ってくれますか?