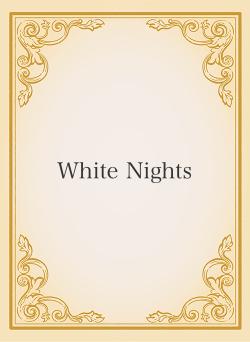相談を受けた時、「好きだ」と打ち明けていれば、
未来は変わったかもしれないのに。
と同時に、ふと思う。
俺らの“幼馴染”とかいう生ぬるい関係も、
もう、終わりか。
あのぬるさが、俺的には最高だったんだけどな。
頬を温かい何かが伝って、
慌ててそれを拭う。
「…リルハ、ごめん」
沈黙が流れたあと、突然聞こえてきた桃の声。
予想もしなかった、
その、言葉。
「俺、彼女いるんだ。そいつのこと、俺は大事にしてるから」
うそ、だろ。
その時の桃に、なんだか俺の気持ちまで踏みにじられた気がして、
俺は駆け寄り、リルハの腕を取ると、その場を走り去った。
たどり着いたのが、「Bar rainy」。
俺はただ、
泣きじゃくるリルハの背中をさすっていた。