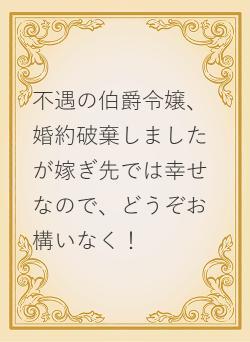「普段そんな事してないだろ?ありがとう、リュウ」
リュウは、俺が声を掛けることを見越して最初に彼女が飲んでたカクテルをつくって置いてくれた。
持つべきものは気心知れた友である。
そうして半ば強引に三杯目を一緒に飲んだ彼女の話を聞けば、前の男はなかなか酷く、それを相手にする彼女の友人も程度が知れている。
彼女が傷つくことは無いと思うし、彼女の苛立ちと悔しさをどうにかしてやりたかったのに聞くことくらいしか出来なかった。
けれど、俺に話した彼女は話した事でスッキリしたのか来た時とは比べ物にならない明るい笑顔を浮かべたのだ。
その笑顔の破壊力たるや。
BARの中がさらに静かになった程だ。
本人無自覚だからタチが悪い。
これは、このまま帰せない。
それに帰したくない。
俺は彼女が欲しいのだ。
立ち上がった彼女の腕を掴み、声を掛けた。
「待って。今日君に一目惚れしたと言ったら君は信じる?」
初めてのアプローチ、俺は内心かなり緊張していた。
心臓が飛び出るのではと思うほどだ。
彼女は少し考えて、口を開いた。
「人の話が聞ける貴方だから、信じてもいいわ」
そう言ってくれた彼女を離さず、俺はホテルに向かい彼女を優しくかつこれでもかと激しく抱いた。
何時になく本気になった、そんな初めての相手。
愛しい。愛してる。
何度も囁いてきつく抱き締めていたはずだった。
即物的過ぎたから起きたらきちんと話をしよう。
寝てしまった彼女の顔を眺め、抱き締めて眠りについた。
翌朝、冷たくなったベッドに一人、俺は間違えた事を認識して激しく後悔した。