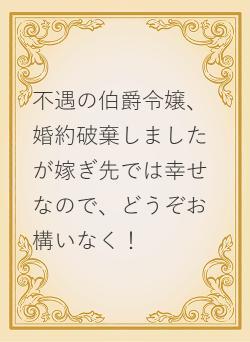その日はそれで解散した。
なんとか保っていたとは思うのだが、春子には私の精神的疲弊が伝わったからだろう。
一緒にケーキを食べてお茶ができたからか、谷村くんは満足そうに帰って行った。
家に着いて部屋に入って私は試験の疲労とは別の疲労でベッドに寝っ転がる。
「うっかり、毎年参加せずに帰宅してたから忘れてたよ。後夜祭の存在を……」
ひとり口に出しつつ、今年も逃げられないものかと思案するもなにせ相手は場合に応じて都合よくタッグを組んで攻めてくるのだ。
二対一では勝ち目がない。
なにしろ、頭脳も行動力も相手の方が一枚上手なのだから……。
「まったく、私なんかのどこが良かったんだか。普通なのにね……」
完全自室という自分のテリトリーでひとりごちる。
仕方ないだろう。
「初恋もまだなのにさ、好きってどんな感じなのさ!」
あまりにも独り言が大きかったらしい。
偶然居合わせた兄が廊下から答えた。
「恋は理屈じゃないな。気づいたら落ちてるもんさ」
実に珍しく詩的な言葉を言った兄は、そのまま出かけて行ったようだ。
なるほど。
「落ちるものねぇ。だから、もっとわかりやすい表現ってないもんなのかなぁ」
私のため息はこの日大量生産されたのだった。