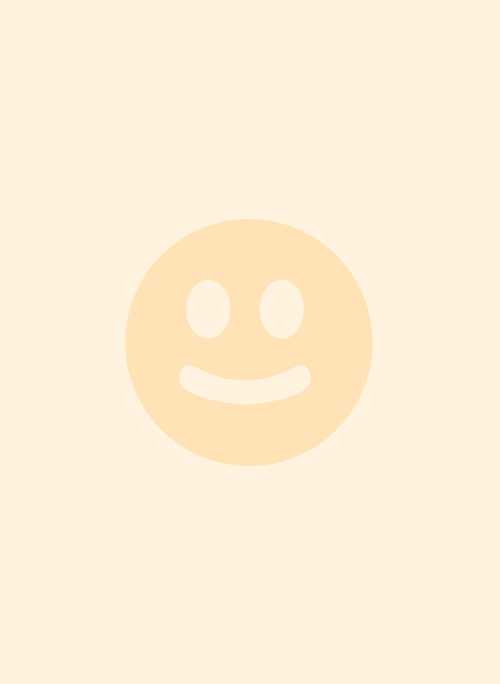集団のランクを無遠慮に蹴散らし、自分は無傷なまま、いろんなところにこれまた無遠慮に踏み入り、平気な面して笑っていやがる。
憎らしいくらいに「俺」と同じなのに、腹立たしくも「俺」とは対照的な大バカ。
空気を読まないことなんて知ったことかと、辺りかまわずぶっ壊し、あたかも開き直っているかのようなソイツの名は香田正人といった。
必然というか、ソイツにとっては当たり前だったのだろう。
香田は俺にも、まれに見るほどの他意のなさでちょっかいをかけた。
それは特に嬉しくはなかったが、やはり寂しくはあったのだろう。
俺は香田に精一杯、憎まれ口を叩くようになった。
俺の孤立っぷりは増したが、やはりそれでも香田は俺にちょっかいをかけるのをやめなかった。
そして、俺はこの時初めて、自分以外にも「こういう奴」はいるものなのだと、いるのも悪くないものなのだと知ったのだった。