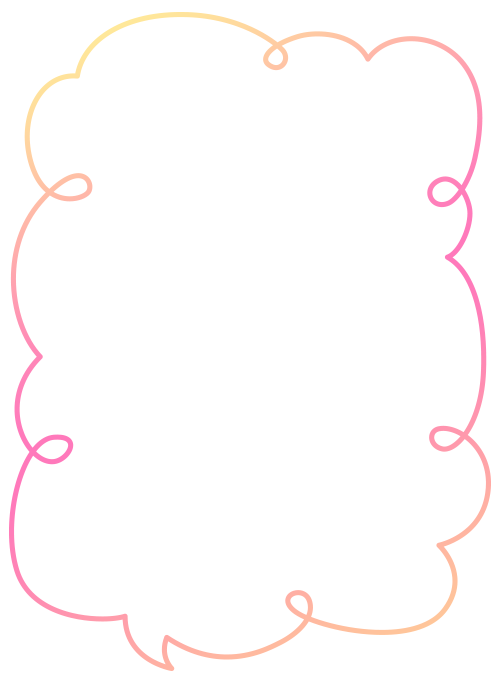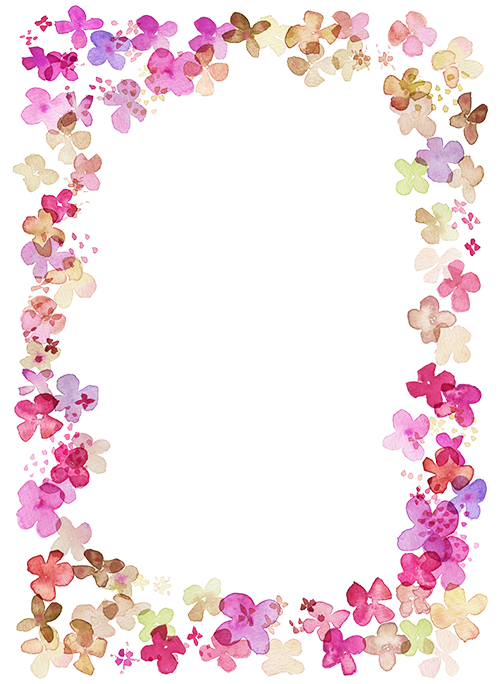「ぐうぅぅ!!うーーー!!」
顔をこれ以上ないほどに歪めた父親と一部始終を目撃して顔面蒼白の母親。
剥がされた部分からはじわっと溢れ出した真っ赤な鮮血がフローリングの床に滴り落ちる。
目の前で起きているその出来事が信じられない。
あ然とするあたしの目の前で今度は母が同じことをされた。
それを止めることもできずに呆然とする。
どうしてこんなことになっているのか、考えたくない。
現実逃避とはこういうことを言うんだろうか。
両親はあっという間にすべての足の爪を剥がされた。
ボロボロと涙を流している両親は里子の両親にすがるような目を向ける。
「どうしたの?助けてほしいのかしら……?」
里子の母親の言葉に両親がこれ以上ないというほどの勢いで首を縦に振る。
すると、里子の父親はにんまりと笑った。
「さすがに両手両足の爪を剥がされるのはきついか。じゃあ、選択肢をあげよう。娘を救うために自分たちの両手の爪を剥がされるか、娘の両足の爪を剥がすか。どちらがいい?それが終わったら僕たちは警察に自首する。それで君たちも解放しよう」
ちらりと両親があたしに視線を向けた。その途端、両親の目に光が宿った気がした。
まさか……、そんなことありえないよね?
だって一応あたしの親でしょ?ここまで一緒に暮らしてきた家族じゃない。
「じゃあ、聞くよ。自分たちの爪を剥がされたい?」
その言葉に両親は黙っていた。
「えっ、ちょ……嘘でしょ!?ねぇってば!!」
「それとも、娘の両足の爪を剥がされたい?」
その言葉に両親は迷うことなくうなずいた。
なんでよ……。どうして……?
「もう一度、確認だ。娘の爪を剥がしてもいいんだね?」
里子の父親の言葉に、両親は『早くやれ!』とばかりに何度もうなずいた。
両親の顔にはもうすぐこの苦痛から逃れられるという希望さえ感じられる。
今、目の前で娘が自分と同じ痛みを味わうことを知っていながらどうしてそんな表情ができるんだろう。
親は子供に無慈悲の愛を捧げるものではなかった……?
ああ、そうか。そうだ。あたしは一度だってアイツらに愛情なんて与えてもらったことはなかった。
唇がブルブルと震えた。自分の意思に反してあたしは涙を零していた。
これが現実だ。現実なのだ。
17年間生きてきて、今、ずっと目を反らしてきた現実を見せつけられた。
顔をこれ以上ないほどに歪めた父親と一部始終を目撃して顔面蒼白の母親。
剥がされた部分からはじわっと溢れ出した真っ赤な鮮血がフローリングの床に滴り落ちる。
目の前で起きているその出来事が信じられない。
あ然とするあたしの目の前で今度は母が同じことをされた。
それを止めることもできずに呆然とする。
どうしてこんなことになっているのか、考えたくない。
現実逃避とはこういうことを言うんだろうか。
両親はあっという間にすべての足の爪を剥がされた。
ボロボロと涙を流している両親は里子の両親にすがるような目を向ける。
「どうしたの?助けてほしいのかしら……?」
里子の母親の言葉に両親がこれ以上ないというほどの勢いで首を縦に振る。
すると、里子の父親はにんまりと笑った。
「さすがに両手両足の爪を剥がされるのはきついか。じゃあ、選択肢をあげよう。娘を救うために自分たちの両手の爪を剥がされるか、娘の両足の爪を剥がすか。どちらがいい?それが終わったら僕たちは警察に自首する。それで君たちも解放しよう」
ちらりと両親があたしに視線を向けた。その途端、両親の目に光が宿った気がした。
まさか……、そんなことありえないよね?
だって一応あたしの親でしょ?ここまで一緒に暮らしてきた家族じゃない。
「じゃあ、聞くよ。自分たちの爪を剥がされたい?」
その言葉に両親は黙っていた。
「えっ、ちょ……嘘でしょ!?ねぇってば!!」
「それとも、娘の両足の爪を剥がされたい?」
その言葉に両親は迷うことなくうなずいた。
なんでよ……。どうして……?
「もう一度、確認だ。娘の爪を剥がしてもいいんだね?」
里子の父親の言葉に、両親は『早くやれ!』とばかりに何度もうなずいた。
両親の顔にはもうすぐこの苦痛から逃れられるという希望さえ感じられる。
今、目の前で娘が自分と同じ痛みを味わうことを知っていながらどうしてそんな表情ができるんだろう。
親は子供に無慈悲の愛を捧げるものではなかった……?
ああ、そうか。そうだ。あたしは一度だってアイツらに愛情なんて与えてもらったことはなかった。
唇がブルブルと震えた。自分の意思に反してあたしは涙を零していた。
これが現実だ。現実なのだ。
17年間生きてきて、今、ずっと目を反らしてきた現実を見せつけられた。