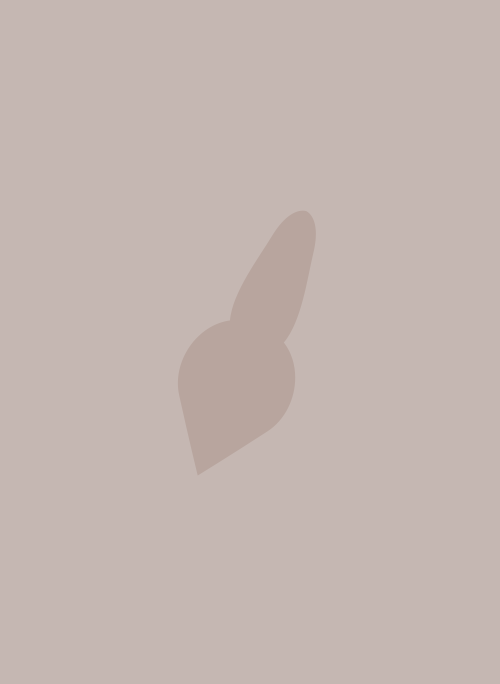日本よりはるかに寒いと実感しつつ、それ以上に韓国に着いて驚いたのは、珉珠の母親が、あのキムおばさんだったこと。
そのキムおばさんも、はじめは知らなかったと言う。
あの〝イ・ジュン〟と高柳グループの御曹司、高柳由弦が、同一人物であると分かったのは、珉珠の結婚式の日だった。
由弦が漢江に飛び込んだあの日。
色んなことがあった。
そしてキムおばさんの名前を、今日初めて知った。
当時ずっと、彼女のことを、「キムおばさん」としか呼んでいなかったから。
今由弦の目の前に、笑って珉珠とキムおばさん、ヤヒ(世姬)がいる。
豪華なご馳走が並び、体の芯から温まりそうなスンドゥブ鍋がど真ん中に置かれていた。
それらを食べながら、キムおばさんが自分におかずを取ってくれる。それも何度も。
最初はその行為に由弦は、違和感を覚えたが、珉珠が、「あなたにたくさん食べてね」とういう最高の愛情表現よと教えてくれた。
何となく分かっていたが、改めて教えてもらうと、由弦は胸が熱くなった。
熱さと辛さに、また胸がいっぱいでそうなったのかわは分からないが、由弦はむせた。
でも味は絶品だった。
思えば母を亡くしてから幼い頃、こんな暖かな場所で、身も心も温まるご飯を食べたことがなかった。
まして、こんなたくさんの料理を囲んで、大好きな人が傍にいて。
キムおばさんの優しが、母と重なり、あの時と同じように、また涙を誘った。
涙を流しながら食べている由弦を見て、珉珠も、珉珠の母ヤヒも、涙ぐませた。
「あらあら、体が温まっただけでなく、目からも汗が出て来たの?」
ヤヒはそう言って、由弦の涙を拭った。
「オレ、あの時本気でキムおばさん家の子になりたいと思ってたんだ。おばさんはいつだって温かく迎えてくれた。嬉しかったんだ」
ヤヒはうなづきながら聞いていた。
「でも今はならなくてよかったって思ってる」
「どうして?」とヤヒ。
「だって、おばさんの子になったら、珉珠さんと結婚できないから」
「あら!?うちの娘をお嫁にもらってくれるの?」
そう返したヤヒに対して、
「はい!いや、それはまだ内緒。彼女にも言ってないから」
照れくさげに由弦は言った。
「そうなの!?でもそうなったら、可愛い息子が一人増えるわね」
珉珠は二人のやり取りを、そばで笑って見ていた。