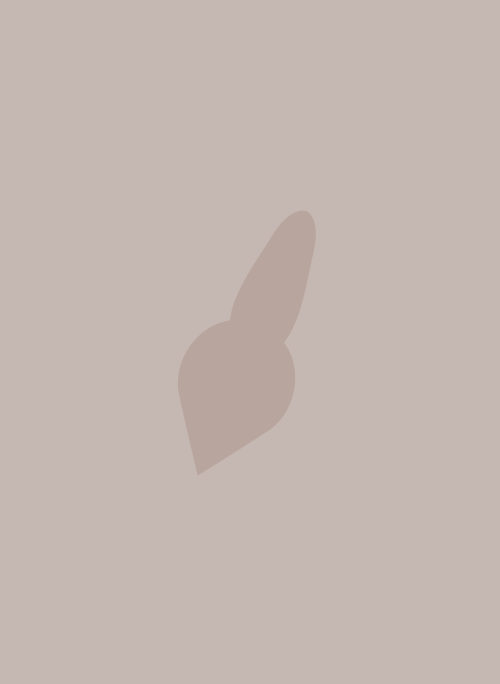ちょうどそこへ、本社から珉珠が来ていた。
今は社長である弦一郎の秘書をしていた。
今回、様々な報道がされる中、落ち込んだ高柳グループを、社員が一丸となって盛り立ててくれたと、社長直々に、感謝すると共に、これからも力を貸してもらいたいとお願いに来ていた。
その報道の渦中にもいる珉珠と、仲里は話す機会を持てた。
普段なら、自分のプライベートのことなど話さない珉珠だったが、なぜがこの時は、素直に仲里に話せた。
自分の母親が経営するボランティア事務所に、長年、寄付をしてくれる人の話をすると、
「私なら、迷わずそれが、高柳専務だと思いましたよ!選択肢から外すこともなく、何の疑いもなく。高柳専務を誰だと思ってるんですか?あの人は、類まれな天才ですよ!ファンの一人として言いますけど、見くびり過ぎじゃないですか!?」
自分が思いもしなかったことを、あっさりと仲里は答えた。
「ほんとに……私はバカだわ。あとになって、全てが明らかになるなんて。想定の範囲内の中で、事実を突き止め証拠や結果を出す。そんなやり方しかしてこなかった。何でも分かり切っていた気になっていただけ」
「なら、そんなやり方やめればいいじゃないですか。青木さんがそんな風になったの、どうせ副社長仕込みでしょ?自分の感情を抑えるのは仕事の時だけで十分だと思いますけど」
「そんな簡単にはいかないわ」
「なぜです?高柳専務に惹かれたってことは、少なくとも、青木さんにも、高柳専務と似た情熱を持ってるってことじゃないですか?」
「……!!」
そんなこと思いもしなかった、仲里の言葉に珉珠は驚いた。
「本当にこのままでいいんですか?心配じゃないんですか?高柳専務のこと。記憶だってまだ戻ってないのに。高柳さん、この寒空の下、どこにいるんだろう……青木さん?寄付した人が、高柳専務だったって聞いた時、どんな気持ちでした?心震えませんでした?私ならその事実を知ったら尚更その人を離したくないと思います」
由弦の口からパク・ジュウォンと聞いた時は、気が動転するほど頭が回らなかった、そしてあとから、「やっぱり彼だ!由弦らしい!」そう思えた。その事実がどんなに嬉しかったか、表現できないほどだった。