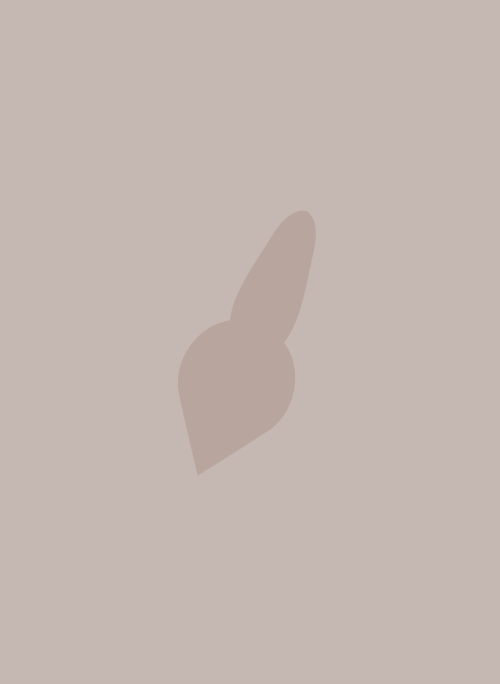「でも、どうして、パク・ジュウォンだなんて名前で寄付をしたの?」
「ん~、何となく、何か地元の人間ぽくない?」
「ふっ、由弦ったら。じゃぁ、その事務所にいた時は、何て名乗ってたの?」
「イ・ジュン」
―――― やっぱり!!
由弦が言ったあと、疑問だったものが全て解け、頭や胸の中にかかっていた靄が、晴れて行くようだった。
「出来ることならあのままおばさんの子供になりたかったよ。おいしかったんだ~!おばさんの作るご飯!一緒にキムチも漬けた!辛いけど美味しかった!とっても温かい人だったんだ」
母親を亡くしてからずっと一人で生きて来た由弦にとって、「おばさん」の存在は母のように大きかった。
優しく大きく包んでくれた、いつも笑顔で迎えてくれた、唯一の人。
「由弦……あの時、本場でトッポッキを食べたことがあるって言ってたの、その時だったのね?」
「えっ!?オレ青木さんにそんな話したっけ?」
「えぇ、随分前にね?」
ほとんど独り言のように呟いた。
初めて二人きりで食事をした日のことを、珉珠は思い出していた。
—————— どうして私は、母の事務所に寄付をして来た、あらゆる人の選択肢の中から、あなたを外したんだろう。ずっと傍にいたあなたを。私はあなたの才能でさえ見くびってた!?自分の母親ともすでに出会っていたのに……私は、なんて愚かなんだろう。今頃になって気付くなんて。
珉珠は心の中で嘆いた。
そして、そのボランティアを経営するのが、自分の母親だと言い出せなかった。
「青木さん……青木さんは今、好きな~」
由弦が何か言おうとして、その問いかけに、珉珠も耳を傾けようとした時、扉の開く音がした。