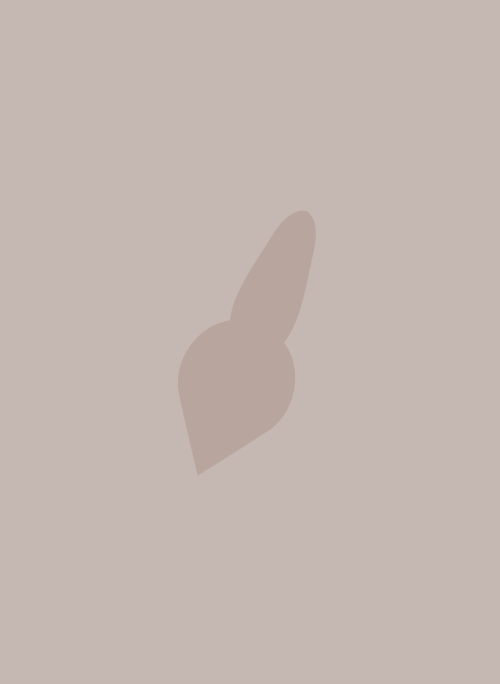「オレが、七つか八つの時だったか、ある人のブログを偶然見つけて、その人のお母さんがボランティア活動されていて、オレそれにとても感動して、いつかそこで何か手伝いたいって思うようになって、それから、十五になった時だったか、そのボランティア事務所に手紙を送ったんだ。そしたら返事が来て、実際会って話したんだ。それがきっかけでそこで、色々お手伝いさせてもらうようになった」
―――― まさかっ!!
珉珠は衝撃が走った。
あるブログとは、珉珠がまだ高校生だった時にやっていたものだった。
普段の自分の生活や、両親がやっている仕事のことだったり、その中で、父が日本で働いていること、その影響で自分も日本に強い憧れを持っていたことや、母がボランティア関係の仕事をしていて、それにもとても関心を持っていたことなどを綴っていた。
それを偶然、由弦が見つけた。
きっかけは、珉珠のブログだった。
全てはここから始まっていた。
「それで!?」
「うん、それで、炊き出しとか、他の施設を回ったりして、色んな企画立てて色んな人たちと触れ合って、とても楽しかった。キムおばさんはオレをホントに可愛がってくれた。キムおばさんって人は、そのボランティア事務所を経営してる人なんだ」
—————— キムおばさん……母のことだ。
珉珠はさらにドキッとした。
「あ、日本で頑張って働いてる娘さんの話もよく聞かされたよ。自慢の娘だって言ってた」
「そうなの?」
珉珠は胸が熱くなった。
「うん!それから数ヶ月ほどで、父さんが迎えに来た。アメリカにいる時なんか顔すら見に来なかったのに。韓国は近いから!?連れ戻しに来たのはほぼ強制だった。それでそこでの、オレのボランティア活動は終わった。でもその後も何か力になりたくて、色々考えて、そこで思い付いたのが寄付!」
「寄付!?お金を?」
「うん!自慢じゃないけど、オレ、既にその頃から、デザイン画が色んな企業の目に留まって使って頂いてたんだ。契約したこともある。そのお金を送ってたんだ。高校生の時のオレ凄かったんだぜ!大学になる頃には、さらに大手企業ともコラボしたり、仕事の依頼をたくさん頂いて、またその頃会社も立ち上げたりして、さらに大金を得られるようになった。だから、ずっと寄付を続けられた。恩返しがしたかったんだ。家族みたいに接してくれたみんなに、おばさんに」
珉珠はこの事実に、運命すら感じた。
そして、母の言っていた、あの少年が、由弦だとこの時初めて分かった。