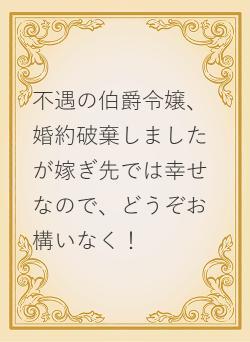「モネ。僕はモネを愛してるよ。僕は君に隣に居てほしい。僕と結婚してほしい」
その目は真剣そのもの。
椅子を立ち私の前に来て、私の手を握り、膝をつく。
「貴族との付き合いもある、王太子妃になるために教育も受けなければいけない。苦労することもあるし、今より自由な時間は減るからドレス作りに割ける時間も減ってしまう。そういう事を分かっていても、僕はモネが良いんだ。モネは僕をどう思ってる?」
一緒にいるのは、心地良い。
ジュール様は終始私への気持ちは隠していなかった。
それが嫌ならば、きっと私は早々に会う事を辞めていたと思う。
私の好き嫌いは結構ハッキリしている…
それはジュール様も一緒に居て理解してきているはずだ。
それでも聞くという事は…
そう、私自身もあえて曖昧にしていたことをハッキリさせる為に切り出したのだ。
私はしっかりと見つめて言った。
「今は、侯爵令嬢だけれど、元々の私は一般市民と同じだよ?庶民だよ?放っておいたらずっと布弄り続けるような引きこもりみたいな感じだし…。そんな私でいいの?」
この期に及んで尻込みする私。
ジュール様はそんな私に柔らかく微笑んで言った。
「そんなモネも、夜会で見せ付けるようにダンスする果敢な所も、家族を大切に思っている所も。見てきたモネ全てが愛しいんだ。僕もその中に入れて欲しいんだよ」
もう、完敗である。