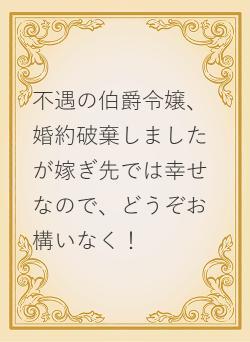その、マノンの一言に私は頭を抱えた。
異世界である、このヴィーノ王国に来たばかりの私はまだまだこの国の身分制度をしっかり理解していなかった。
まさか、王家が私を王太子妃にと望めばそれが家格的にすんなり通るとは知らなかった。
「それは、私が養女であっても変わらないの?」
「家柄がものを言いますからね?養女でもシュヴァイネル家に名を連ねていれば、なんら問題はありませんね」
マノンさんはそう答えた。
私は、どうにも逃げ出せそうにはない現実を受け入れるしか術が無いようで、それはそれは大きなため息をついた。
「王太子妃になんて、こんな針仕事大好き娘が向くわけないのに…」
このつぶやきには、うちのお針子さん達は苦笑しつつも何も言わなかった。
とりあえず、私が望まぬ方向に進み始めた事態は、私では止めることなど叶わないことだけはしっかりと理解した。
故にレース編みに逃亡する私を、皆は暖かく見守ってくれた。
その優しさに甘えて、私はこの日、つけ襟三つとコースター五つを編み上げたのだった。
逃げに逃げた現実逃避の賜物は、その後しっかりと我が家で使われていたりする。