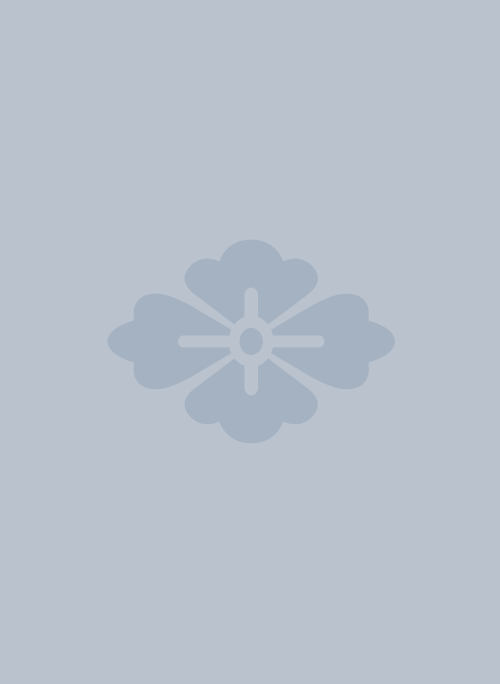「──なかなか良い腕をしているね」
ふと、雨の音の中に低くも高くもない不思議な声がした。
顔上げれば、そこには傘を差しながら男の体を覗き込む男がいた。
「誰だ?」
「僕は切碕。……君、彼を殺したとき、どんな気持ちだった?」
殺したときの気持ち?
そんなの覚えていない。
でも、手には命を奪った感覚が残っている。
「……気持ちは覚えてねぇけど、感触は手に残ってる」
「どう?その感触は?」
傘から現れた男の姿に、俺は一瞬呼吸が止まったような感覚に陥る。
その男……切碕は紅い両目をした恐ろしく整った顔をしていた。
「どうだったの?その感触……」
問い質すような口調に俺は深く息を吸うと、深く息を吐き出した。
「異常者に思われるかもしんねぇけど、気持ち良かったよ……」
喧嘩ばかりして手の骨に顔や体の骨がぶつかる感覚には飽きていた。
でも、今日初めて知った肉を断つ感触……。
それは今までに感じたことのない程の気持ち良さがあった。