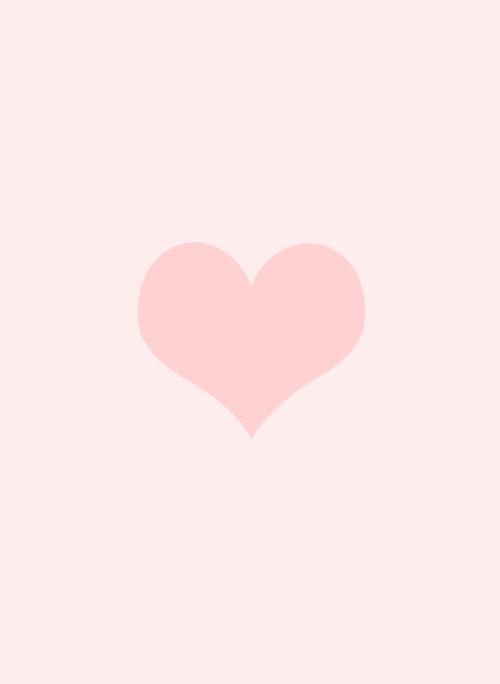「それで、なんで『お歳暮』なんですか?」
「あれは、本当はお中元のお返しに用意したもので……渡せなくて」
「臆病者」
「……俺なりに頑張ってたんだけどな」
大通りを車が流れる音がする。
剥き出しの足首から冷気が全身に回っていく。
小川さんの腕の中で、ようやく日常の感覚が戻ってきた。
「……ごめん、ミナツさん。さすがに仕事が……」
「やだ!」
「本当にごめん!」
背中に爪を立てるようにしていた腕をやんわり離される。
ワガママを言いながらも仕事が大事なことくらいわかっているので、仕方なく引き下がった。
「お仕事頑張ってください」
小川さんの手を温めるように握った。
手袋をしない小川さんの手は冷たくて、両手で指先を握ってもあたたかくはならなかった。
「ありがとうございます」
小川さんはバイクに股がり、再びエンジンをかける。
「昨日のカフェで、俺絶対振られたと思われただろうなー」
「だったら、今度手を繋いで行けばいいですよ」
「そうですね」
小川さんはもう一度私の頭に手を置いて、行ってきますと仕事に戻っていった。
どこにでも手を繋いで行ったらいい。
何回でも手を繋いで行ったらいい。
その手が冷たいとかあたたかいとか、いつもわかる距離にいたい。
部屋でひとり、小川さんからの包みを開けてみた。
「……ロマンチックすぎる」
シックなベージュにブラウンのリボンという高級感がある箱の中からは、コーヒーカップが出てきた。
逆三角形のような優美な曲線を描いているのは透明なガラス。
持ち手は金属なのか粘土なのか、とにかくガラスではなく、うすいピンク色のバラが咲いていて、蔦が絡まっている。
ソーサーも透明なガラス製で、そちらには白い小さな蝶々が止まっていた。
私とはほど遠いけれど、見たことないほど繊細できらきらしたコーヒーカップ。
昨日から涙腺の調子がおかしい。
カップの中には、コーヒーより先に涙が注がれた。
愛されている。
私はちゃんと愛されている。
言葉ではなく示してくれた愛情を今、確信した。