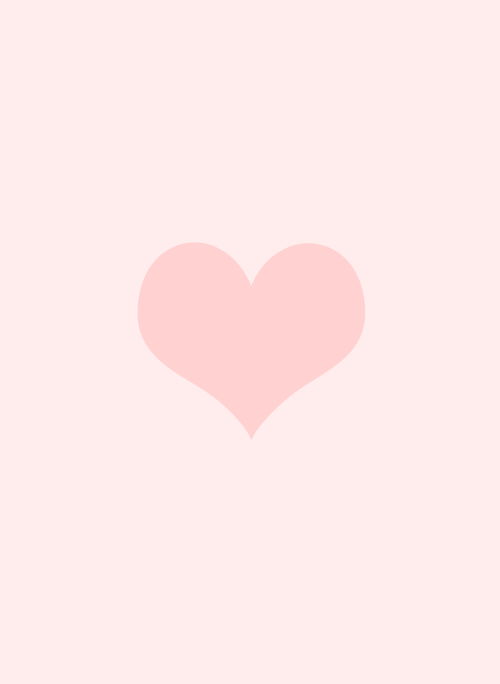「ミナツさーん」
大きなバイク音と雨音の向こうから、私を呼ぶ声が聞こえた気がして足を止める。
「ミナツさーん」
どんどん大きくなるバイク音と声。
そして真横に真っ赤な箱をつけたバイクが停まった。
水が跳ねないように、そろそろとやさしく。
「ミナツさん、傘忘れたんですか?」
突然現れたずぶ濡れの配達員さんは、滴に濡れた顔で私を心配そうに覗き込んだ。
「あ、えーっと。こんにちは」
これまでの惨事は一言では話せず、つい口ごもる。
ところが返事なんて待つつもりはなかったようで、彼はもどかしそうに焦りながら箱の隅からモスグリーンのタオルを取り出した。
「これ、使ってください」
「え……でも……」
あなたは? という言葉はふわりとかぶされたタオルに吸い込まれた。
タオルはまったく濡れておらず、降る雨から私を守ってくれる。
「俺は慣れてますから。濡れるのも仕事みたいなものなので」
確かに雨対策はしっかりなされた服装だったけれど、それでもえくぼまで濡れていた。
「本当なら送ってあげたいところだけど、すみません。そのタオル、使ってないから汚くはないです、多分」
タオルからはほのかな柔軟剤の香りと、男の人の匂いと、多分箱とか紙とか、いろんな物の混ざった匂いがした。
彼にまつわる雑多なそれは、新品のものよりどこか私を安心させる。
「使い終わったらポストに引っかけておいてくれればいいので。今度回収しますから。ほら、早く帰らないと風邪引きますよ」
言うだけ言って、彼はバイクをくるりと回転させた。
仕事のルートからはずれて、わざわざ来てくれたらしい。
「ありがとうございましたー!!」
走り出した背中に叫ぶと、少し振り返って会釈してくれた。
遮る雨で見えなかったけど、彼ならきっと笑顔だっただろう。
前髪からぽたり、ぽたり、と滴が落ちていく。
それがきらっと輝いた気がして頭上を見上げると、雨雲にしては規格外に空は明るかった。
雲の隙間から太陽の欠片が漏れ出すように、雨粒はかがやきながら降りてくる。
そこから歩いて5分。
親切心はありがたくても、タオル一枚で防げる雨ではなく、結局ずぶ濡れだった。
だけど、今にもこぼれそうだった涙は、不思議とどこかへ消えていた。
「さすがに、何かお礼しないと」
当たり前だけど、何が好きとか苦手とか、何も知らない。
彼は私の家も名前も知ってるというのに。
「あ、名前も知らないや」
バイクの箱にも番号しか見えなかった。
郵便局に問い合わせればわかるのかもしれないけれど、さすがにやり過ぎだろう。
何が好きなんだろう?
何なら迷惑にならないかな?
泣くはずだった時間はわくわくとした気持ちで埋め尽くされた。