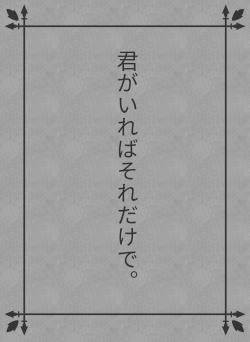ただ、本人が頑張っていただけの話。ずっと見てきた俺たちにはいつ怯えているのかなんて分かり切った話だった。きっと怯えなくなった後から一緒に過ごし始めたカーレイジでも今回、様子がおかしい事くらいは気付いていただろう。
国王に一礼すると、ハウラムは俺を連れて書斎から離れた。冷静を装っていても内心、お嬢ちゃんの事が心配で仕方ないのだろう。歩く速さがいつもの倍になっている。
「俺たちも早く戻りましょう」
「なぁ、ハウラム。今、一番疑われるのは俺かお前さんだ。一応訊いておくが、お前さんはやっていないんだな?」
ハウラムは俺に犯人なのか問い掛けられても俺の目を真っ直ぐ見る事が出来た。曇りの無い目で真っ直ぐ俺を見れたんだ。ハウラムはきっと、本当にやっていない。だってハウラムは思惑通りに事が進む時、にやりと笑うのだから。
国王に一礼すると、ハウラムは俺を連れて書斎から離れた。冷静を装っていても内心、お嬢ちゃんの事が心配で仕方ないのだろう。歩く速さがいつもの倍になっている。
「俺たちも早く戻りましょう」
「なぁ、ハウラム。今、一番疑われるのは俺かお前さんだ。一応訊いておくが、お前さんはやっていないんだな?」
ハウラムは俺に犯人なのか問い掛けられても俺の目を真っ直ぐ見る事が出来た。曇りの無い目で真っ直ぐ俺を見れたんだ。ハウラムはきっと、本当にやっていない。だってハウラムは思惑通りに事が進む時、にやりと笑うのだから。