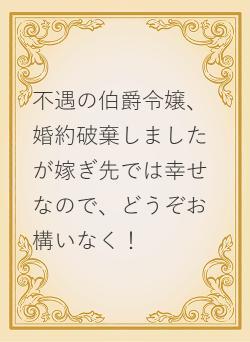「なにかあったとしても、それは過去のことで過ぎてしまったことです。今更、話すことはありません」
俺の問いに、視線を逸らして返された言葉。
話すことは無いという、拒絶。
だが、俺は諦める事なんて出来ない。
彼女が俺の唯一だと、心が叫んでいるから。
「俺は、なにも聞いてない。なにも知らないまま君が消えてしまった時、俺がどんなに絶望したか知らないだろう? 君が大変だった時に一声も掛けられず、頼りにもされなかったことを、俺は心底悔やみ続けている」
俺の言葉に彼女はハッとして顔を上げる。
しかし、そのあと唇を噛み締めて苦しげな顔を俯かせた。
お互いに苦しい顔をしつつも、彼女の言葉を俺は待つ。
すると、彼女の次の声は低く、ひどく冷たかった。
「なにを悔いたんです?」
棘を含む低さに、俺や中嶋先生夫妻も驚いている。
しかし、ここで話さなければ俺は彼女を手にすることは叶わないと、意を決して話す。
「君に俺の気持ちを言葉にしていなかったこと。俺自身の事をしっかり君に話していなかったこと。あの時、君にしておかなければならなかった説明が不足していた事を、君が居なくなって初めて気づいたんだ」
後悔の滲んだ声で、情けなくて仕方無い事実をありのまま彼女に伝える。
「だから、ずっと君を探していたんだ。俺は昔も今もただ一人君だけを愛していると伝えたくて。君を見つけたから、ここに来たんだ。君に俺の気持ちを伝えて君とまた、一から始めたくて」
そう言い切って、俺は彼女を見つめた。
愛しさを隠さずに。