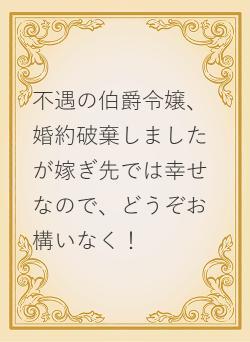「なにかあったとしても、それは過去のことで過ぎてしまったことです。今更、話すことはありません」
そう、視線を逸らして言葉を返す私に先生は苦しそうな声音で話し出す。
「俺は、なにも聞いてない。なにも知らないまま君が消えてしまった時、俺がどんなに絶望したか知らないだろう? 君が大変だった時に、一声も掛けられず、頼りにもされなかったあの時を、俺は心底悔やみ続けている」
その言葉にハッとして顔を上げる。
子どもの事は話してないから、きっと今言ってるのは事故死した両親の話だ。
確かに大変だった。
でも、頼ることなんて出来ようはずもない。
あの時のあなたには、奥さんが居たのだから。
お互いに苦しい顔をしつつ、次の先生の言葉を促すべく口を開いた。
「なにを悔いたんです?」
その声は思ったより低く出た。
棘を含む低さに、先生も、中嶋先生夫妻も驚いている。
「君に俺の気持ちを言葉にしなかったこと、俺自身の事をしっかり話してなかったこと。あの時に君にしておかなければならなかった説明が不足していた事を。君が、俺の前から居なくなって、初めて気づいたんだ」
情けなさそうに、力なく話す姿は確かに後悔の念が読み取れる。
「だから、ずっと君を探していた。俺は昔も今もただ一人、君だけを愛していると伝えたくて。君を見つけたから、ここに来たんだ。君にきちんと俺の気持ちを伝えて、また君と一から始めたくて」
そう言い切って私を見つめる先生はすごく真剣で、そしてその瞳には確かに熱を孕んでいた。