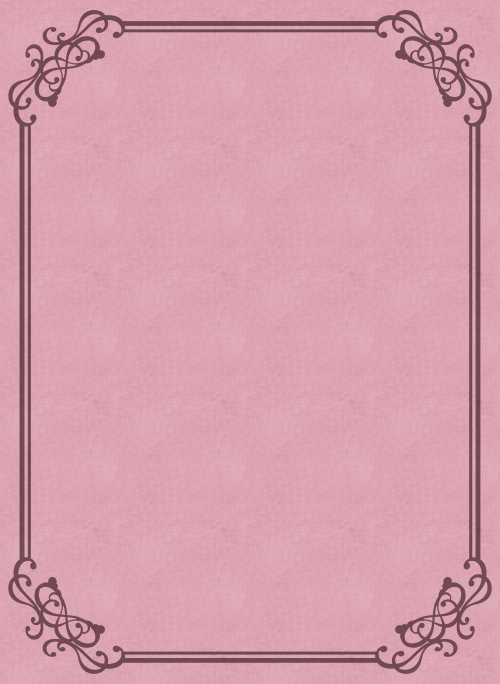ルディガーの口からでたマクシムというのは、ディアヌの父親の名前だからだ。もっとも、顔もほとんど覚えていないけれど。
「困る?」
「だって、ここはシュールリトン王国だもの」
「……そうか、そうだよな」
クラーラ院長には、ディアヌの素性について余人には知られぬようにしろと言明されている。
何に苛立ったのか、どんっとルディガーは地面にこぶしを打ち付ける。それを見ていたら、邪魔をしてはいけないような気がした。
「あの、ごめんなさい……もう、私行くから」
今までうすうすと感じてはいたのだ。修道女達も、父の名前を口にするのは禁じていた。そして、母はディアヌをここに送ったきり会いに来てくれない。
きっと、ディアヌの父は悪い人間なのだ。だから、こんな反応を示される。じわっと涙がにじむのを、なぜか彼には見せたくないと思った。
言葉の後半は、ルディガーは自分に言い聞かせているみたいだった。ディアヌの目からあふれた涙を彼は乱暴な手つきでぬぐう。