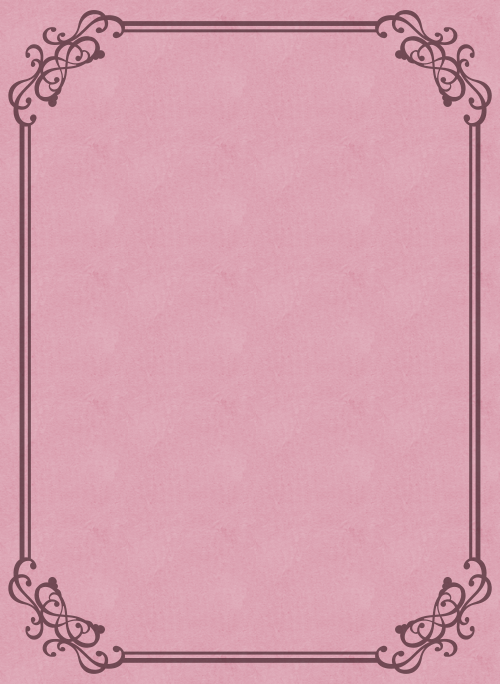父や兄の犯してきた罪を償うために、背負える限りの業はすべて背負っていく。
そう決めたから、ディアヌには迷いなんてなかった。修道院を出て、この城に戻ってきた時から、いつかはこんな日が来るのはわかっていた。
「後悔は——していませんか。もうすぐ、あなたの家族は処刑されます。彼らの処刑のあと、あなたとルディガーの婚儀だ」
「……後悔なんてしません。父の犯してきた罪は、あまりにも大きなものでしょう。私のような女を一時でも妻と呼ばねばならないルディガー、いえ、陛下には申し訳ないと思いますけれど」
その言葉に、ノエルは少しだけ困ったように笑った。彼がそんな顔をすることがあるなんて思ってもいなかったから、なんだか驚いてしまう。
「母が婚儀の時に着用したドレスがあるはずです。それを手直しして——着たいと思います」
本当は、亡くなった異父姉に着せたかったであろうドレス。それをまとうことに良心の咎めがないとは言わない。
誰一人として祝福してくれないであろう婚儀であることはわかっていたから、せめて、母の身体を包んだドレスを身につけたかった。
母は、父に嫁ぐと決めた時、どんな思いで嫁いだのだろうか。愛しい人との間に生まれた娘を守るために、好きでもない男に嫁ぐ。
知らず知らずのうちに、ディアヌは胸の前で手を組み合わせていた。家族を売った自分は間違いなく地獄に落ちるだろう。
ただ、先に処刑されるであろう家族は、少しでも安らかに眠ることができればいいと思った。