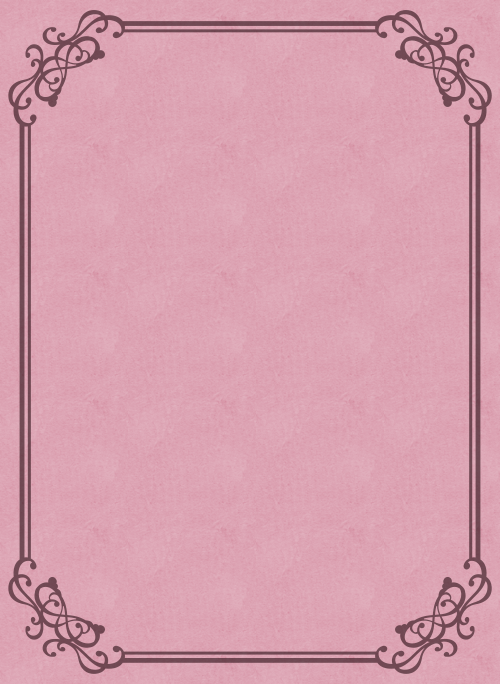理由がどうであれ、裏切ったという点には間違いがない。勝者と共に、そこに戻るディアヌは、周囲の目にはどう映るのか。
考えかけたところで首を横に振る。そんなこと、何度も考えたではないか。
おそらく、城に入ったところで、周囲からは罵詈雑言が浴びせられるのだろうが、今さら気にするようなことでもない。
「姫様、私もお供します!」
「ジゼルを共につれていきたいのですが、よろしいですか?」
「好きにしろ」
ルディガーはそうでもないのだが、ノエルの鋭い視線がジゼルに突き刺さるのが見えた。
「剣を持つのは許さんぞ」
ノエルが、そう告げる。
「かまいません——いいわよね、ジゼル」
不満顔のジゼルがうなずいた。
扉を塞いでいた家具をずらし、部屋の外に出る。
長い廊下を歩き、中庭に出た。
壁は崩れ、あちこちからうめき声が上がり、血の匂いと様々なものが焼けこげる臭いが漂ってくる。
その凄惨な光景から、目をそむけかける。立ち止まりそうになると、ルディガーはディアヌの腕を引っ張った。
「目をそむけるな。これがお前の行動の結果だ」
「……そむけません」
緊張のあまり喉が鳴る。わかっている。この凄惨な光景は、ルディガーに絵図を渡した結果だ。
——この城に戻ってきたのは、十四になった春だった。それから、二年。
見たくない光景を何度も見せられることになった。
父や兄達の機嫌を損ねないよう、常にびくびくしていた城内の者達。
女性の使用人達は皆、父や兄達の目にとまらないよう、顔を汚し、常にうつむくようにして働いていた。
ルディガーの手に城を渡すことによって、今後は少し変化してくるのだろうか。自分の行動が正しかったか否か、答えを出すことができるのはもう少し先になりそうだ。