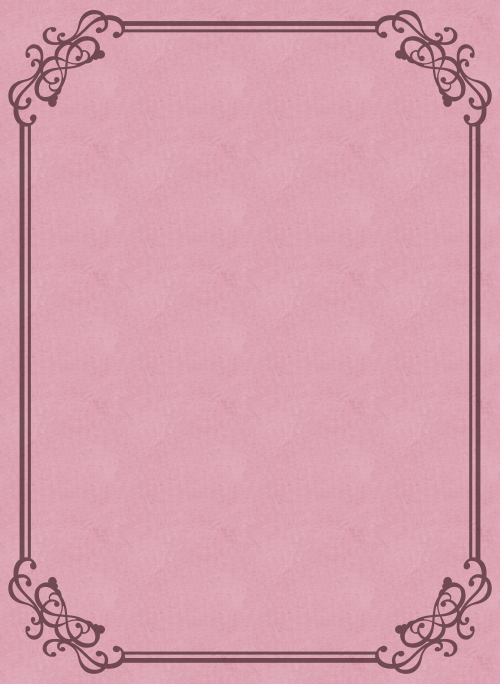「ジュール……お兄様……」
「どこに行っていた?」
「……城壁から、街を見ていました。ヒューゲル侯爵が、戻ってきたようですね」
嘘をついてもしかたがないので、実際の行動を告げる。ジュールは、ふんというなり眉間に皺を寄せた。
若い頃の父と、彼の容姿はよく似ているという。濃茶の髪は、無造作に額に落ち、鋭い目は何も見過ごさないというような光を放っている。
背は高く、しっかりとした筋肉が全身を覆っている。なすすべもなく、彼にいたぶられた使用人が何人もいるのを知っていた。
「お前、何を考えている?」
息が混ざり合うのではないかと思うくらい近く、ジュールは顔を寄せてきた。
「な、何をと言われても……薬が足りません。包帯も。食料も、籠城が続けばすぐに足りなくなるのでは?」
「そんなこと、お前が気にする必要もない」
どん、と肩を押され、二歩、後退する。そのまま倒れ込みそうになるのを、慌ててジゼルが受け止めてくれた。
「——姫様、大丈夫ですか!」
ジュールをにらみつけ、前に出ようとするジゼルを手で止める。一応、異母兄が気を使っているのはわかっていた。これが、他の使用人ならば容赦なく顔面を殴られていたはずだ。
「……そう、ですか。もうすぐ、攻めてくるだろうとヒューゲル侯爵は言っていましたよ。迎え撃つ準備をした方がいいかもしれませんね」
「お前は、どうするつもりなんだ」
「私は……今までと変わりませんわ。傷ついた者達の手当てを。薬が足りなくなりそうなので、どうするかを考えなければ」
失礼、とだけ言い残しジュールの側を通り抜ける。