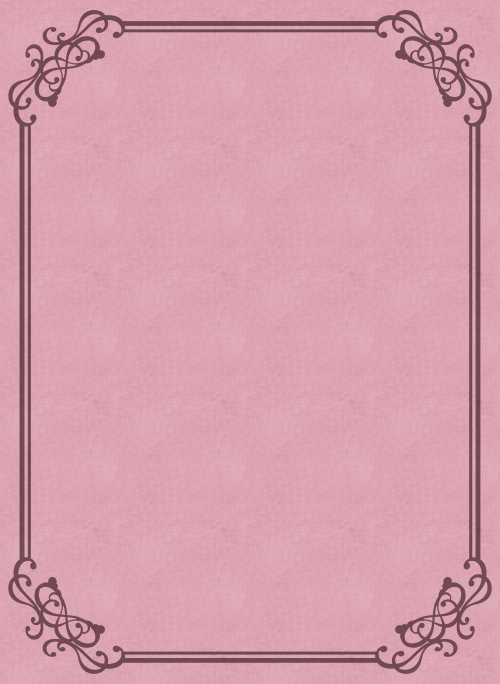「しかたがないでしょう。この城にいてもろくなことはありません。王に殴られるか、王子に殴られるか——殴られてすむのであればまだ運がいい方です。命を落とした者も多数いたはずです」
「……そうね。あの人達にとっては、民など自分の欲望を果たすための道具に過ぎないのでしょう」
城の周囲をぐるりと回る。このところ、セヴラン軍がこちらに迫ってきているということもあり、城は守りを固める準備を整えていた。
兵士達の集まっている場所、食料の保管庫。武器庫——どんな防御態勢を敷いているのか。それさえわかれば、ルディガーはこの城を攻めやすくなる。
「脱出の経路も確保しておかなければね——そこのあなた、どうしたの?」
廊下の隅にうずくまるようにしていた侍女に向かい、ディアヌは声をかける。
「いえ、お見苦しいものを……申し訳ありません」
こちらを向いた侍女の顔は、真っ赤に腫れ上がっていた。唇の端が切れて、そこから血が滲んでいる。
「ひどいことを——誰に殴られたの?」
その問いかけには、怯えたような表情になって、彼女は首を横に振った。おそらく、父か兄——いずれかにやられたのだろう。
相手が、王族でなければ彼女は口を開いたはずだ。
「……こんな傷を負わせるなんて。ジゼル、薬を」
ディアヌの言葉に、無言のままジゼルが前に出る。そうして、彼女はうずくまっていた侍女に薬の入った容器を手渡した。
「この薬は、姫様が調合なさったものよ。大事にお使いなさい」
「あ——ありがとう、ございます」
薬を押し抱くようにして、彼女が頭を下げる。