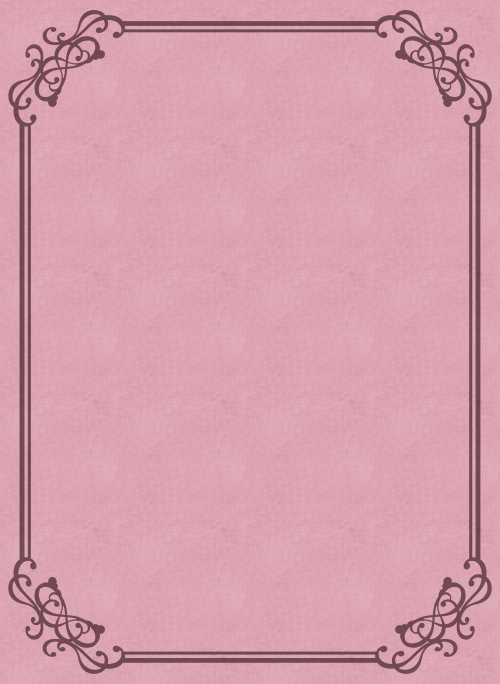「あんたは——ただ者じゃなかったんだな」
「ちょっと、『訳アリ』なだけ。昔……生きていくために、傭兵をしていたことがあってね。今じゃ修道院で院長だけど」
険しかった彼女の表情が、少し柔らかくなった。
「何が修道院で院長だよ。まったく——だけど、あんたがここに身を置く理由もわかったよ。あんたは、あんたなりのやり方で、このあたりの人間を守ろうとしてるって」
「いざって時は、周囲の村人達をここに収容するつもりだったんだけどね。盗賊ごときにこう簡単に攻め入れられてしまうようじゃ、もう一度考え直さないと」
ディアヌには、まったくわからない言葉が院長とルディガーの間で交わされていた。それから、院長はディアヌの前に膝をついた。
「姫様、よくぞご無事で」
彼女の大きな手が、ディアヌの手を包み込む。
自分は、何もできなかった——ディアヌはうつむいた。自分は、ただ、二人に守られていただけ。
「ルディガー、怪我はないね?」
「ああ」
「それなら、すぐにこの修道院を発つべきだ。この修道院が襲われたとなれば、マクシム王の部下がやってくる。その時、ここにいたらまずいだろう」
「どういうことだ? この修道院だってそんな安全じゃないだろう。俺がここにいた方が、少しは役に立つんじゃ」
ルディガーの言葉に、院長は首を横に振る。
「ルディガー・ベタンクール。あなたは父親にそっくりだ——あなたがいなくなれば、セヴラン王家の血はとだえる。そうだろう?」