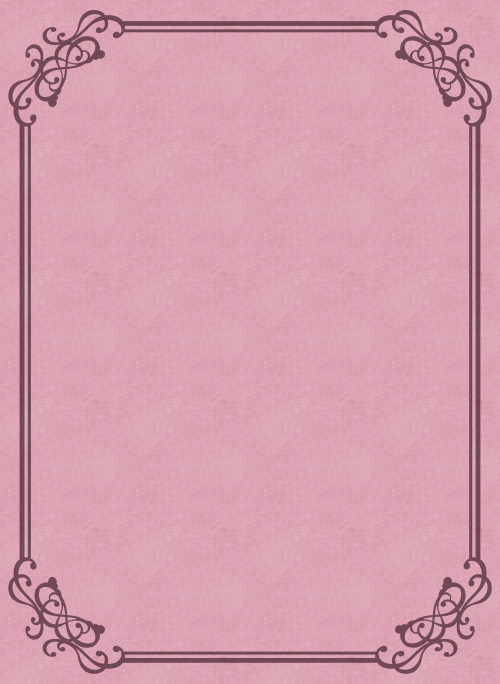「あの女傑が、あの秘密を知っていたらもっと早く証拠を出したに決まっているだろう。俺がマクシムを殺した時にあの証拠を出していれば、ディアヌにあんな思いをさせないですんだ——あれは嘘だ」
「嘘だって……」
まさか、一応現役の修道女となっているクラーラに嘘をつかせるとはノエルも思っていなかったようだ。嘘だってと口にしたきり、口を開けたり閉じたりして言葉を探しているようだ。
そんな彼の肩をぽんと叩き、ルディガーはさらに言葉を重ねる。
「ブランシュ王妃がディアヌを修道院に送ったのは、自分のやろうとしていることを見せたくなかったのではないかと俺は思う。たとえディアヌがマクシムの娘であったとしても、だ」
夫を失い、頼りにした義弟も追いやられ、愛した人の娘も命を落とした。
おそらく、ブランシュにできたのはマクシムの耳に毒めいた言葉をを注ぐことだけ。彼が自滅の道を歩むように、人心が彼からはなれていくように。
おそらく、ブランシュの思い通りに彼は操られたのだろう。かつては野蛮ながらも有能な男であったはずなのに、何もなければあそこまで粗野な男にはならなかったはずだ。
「ブランシュ王妃なりの復讐だったということですか。それで俺に何をさせたいんですか。あなたは」
「ディアヌを守ってやってくれ。もし、俺が先に逝くことになったなら。そのためにも、秘密を知る者は必要だ。なにせ、ヒューゲル侯爵には、こんな秘密を背負わせるわけにはいかないからな」