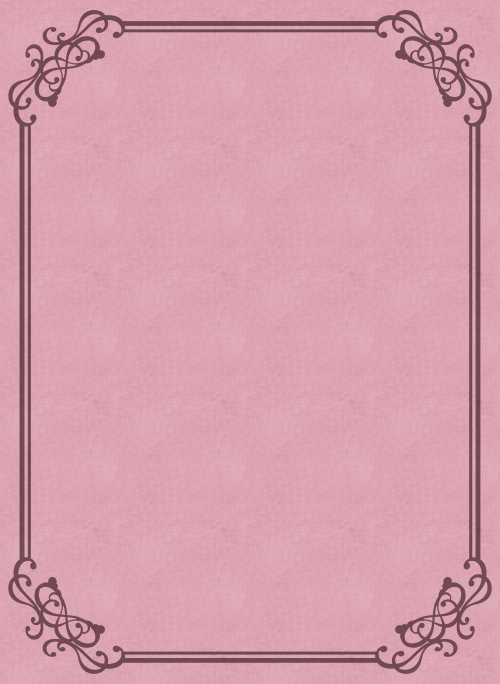その幸せを奪ったのは——自分に半分血を分け与えた父だ。母の若い頃の話を聞けて嬉しかった半面、その直後に待ち受けていた悲劇を思えば、いつまでもこの場にいてはいけないような気がした。
「私は、部屋に戻りますね。そろそろ、時間ですから」
今日は、見習い修道女達が来なかったから、施療院の患者達も心配しているだろう。王の命令で宴会の準備の手伝いに駆り出されると説明されているはずだ。
ルディガーにも一礼し、そのまま静かに部屋を出る。すかさずジゼルがついてきた。すっかり静かになってしまったディアヌを案じているのかもしれない。
「——ディアヌ!」
その声に振り返れば、ルディガーが後から追いかけてきた。ジゼルに先に行くよう目線で合図する。
「どうか、なさいました?」
「もう少し、一緒にいたいと思ったら悪いか」
不機嫌そうに、ルディガーが口角を下げる。そんな顔を見ていたら——心の奥から押し寄せてくるものがあった。
「悪くは、ありませんが——だって、私達……」
自分でも歯切れの悪い口調になっている自覚はある。けれど、母の話を聞いた直後に、そんなよこしまな想いを抱えているなんて間違っているとしか思えない。
「二年が終わる頃には、周囲がお前を見る目も変わるようになるから安心しろ」
「……でも、私は」
母の話を聞かされれば、改めて思い知らされる。母の幸せを壊した父。その父の血を引く自分。
今日、あの席に座っていた間だって、非難のまなざしが突き刺さるのに気づいていた。何も見なかったふりをしていたけれど。