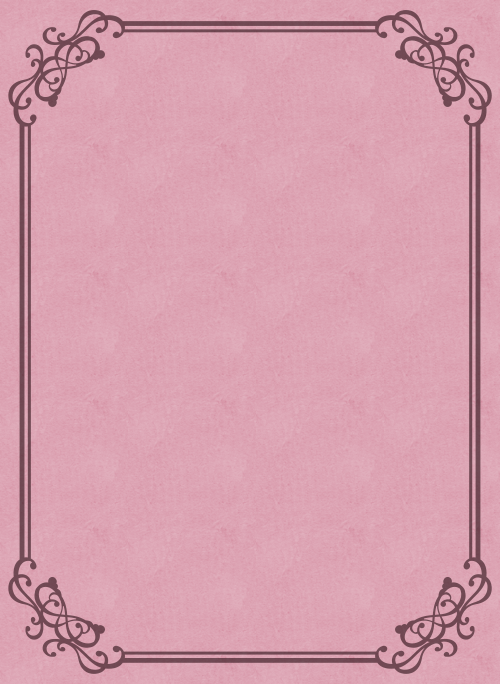「院長のことを、ご存知でした? ええ、元傭兵です。近隣の住民達を守る役も引き受けていて……実を言うと、若い修道女の中には、時折戦に出る者もいるのです。異母兄の手持ちの兵は少ないはずですから——護衛に傭兵を雇う可能性も否定できません。傭兵達は独自の情報網を持っているそうですから、何か知っているかも」
「……そうですか。懐かしい……彼女が、ブランシュ王妃の側にお仕えしていた頃、何度か会ったことがあります。そういうことでしたら、彼女に会う必要もないでしょう。こちらも、傭兵の情報網は握ってますので」
立ち上がったヒューゲル侯爵は、丁寧に一礼した。
「貴重なお話、ありがとうございました——それと、あなたの誕生まで——呪わないでください。あなたの行動によって、助かった者もいるのですから」
「そう思ってくれる人がいるのなら……いいのですけれど。ヒューゲル侯爵……ご武運をお祈りしています」
ヒューゲル侯爵の武運を祈るということは、ジュールがとらえられる、もしくは死亡するということだ。それが何を意味しているのか理解しているから、彼もまた微妙な表情になった。
それでも、もう一度頭を下げて立ち去った彼は、この部屋に入ってきた時と違い、何かを決意したように背筋をまっすぐに伸ばしていた。
彼は、この先ジュールをとことん追い詰めるのだろう。
「……そうですか。懐かしい……彼女が、ブランシュ王妃の側にお仕えしていた頃、何度か会ったことがあります。そういうことでしたら、彼女に会う必要もないでしょう。こちらも、傭兵の情報網は握ってますので」
立ち上がったヒューゲル侯爵は、丁寧に一礼した。
「貴重なお話、ありがとうございました——それと、あなたの誕生まで——呪わないでください。あなたの行動によって、助かった者もいるのですから」
「そう思ってくれる人がいるのなら……いいのですけれど。ヒューゲル侯爵……ご武運をお祈りしています」
ヒューゲル侯爵の武運を祈るということは、ジュールがとらえられる、もしくは死亡するということだ。それが何を意味しているのか理解しているから、彼もまた微妙な表情になった。
それでも、もう一度頭を下げて立ち去った彼は、この部屋に入ってきた時と違い、何かを決意したように背筋をまっすぐに伸ばしていた。
彼は、この先ジュールをとことん追い詰めるのだろう。