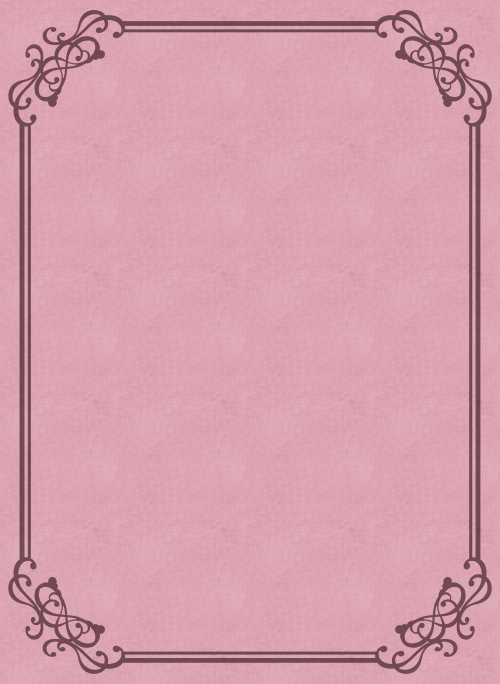「——王太子ジュールか!」
ルディガーの声に、こちらを向いた男は舌打ちしたみたいだった。鮮やかな金色の髪が、兵士達の向こう側に消える。
「——追え!」
本当なら、そこでルディガー自ら行くべきだったのかもしれない。だが、部下達に追わせることにして、彼はディアヌの無事を確認する方を優先した。
そして、行われた婚儀。家族の処刑。
十年前のあの日、命を助けてもらったからというわけではない——たぶん、これは運命だ。
他の女なんていらない。彼が必要とするのはディアヌ一人だけで。
それを自覚したのは、彼女がジゼルと二人、城の敷地の端を掘り返しているのを遠目に見た時だったのかもしれなかった。
——かける言葉も見つからなかった。
忠実な侍女と二人きりで、父と兄を葬る墓を作る。部下に手を貸すよう命じようかとディアヌに言ったら、彼女は首を横に振った。
『父に恨みを持つ者も多いでしょう。遺体を晒しものにしないことに不満を持っている人も多いはずです。その人達の気持ちを考えたら、手を貸すようになんて言えません』
再会して以来、彼女はいつもそうだ。
自分のことよりも、まず、周囲のことを考える。幼い頃から、両親のもとを離れて暮らし、二年前にようやく城に迎え入れられた彼女に罪などないはずなのに。
「——ルディガー様、ヴァレン公爵が目通りを願っています」
「……わかった。トレドリオ王家の復興について、だったな」
今回、戦いを起こすにあたり、ルディガーは旧トレドリオ王家の生き残りの支援を約束した。今、ルディガーがいるこの城は、セヴラン王家のものとなる。