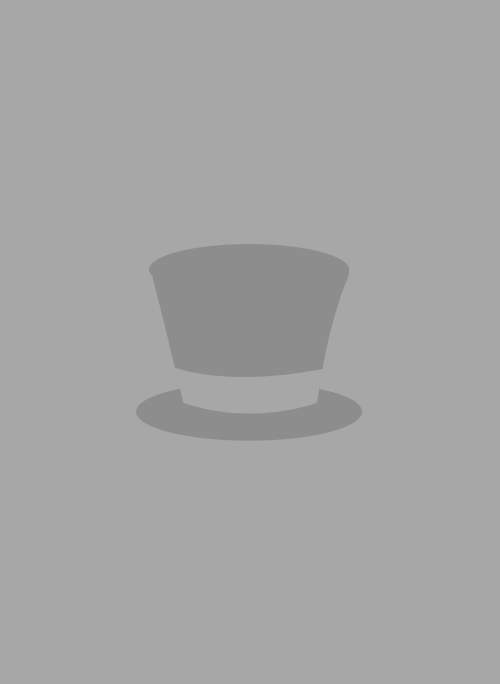ザー・・・
雨がうるさい。
耳の鼓膜を突き破って、頭に刺さりそうだ。
ベットにあがって、少し高い窓辺に腰をかけ、片足はだらんと下に降ろし、ぼーっと外を見つめる。
何もしていない、考えていないのに溢れてくる涙。
それがどういう感情からなのかも私にはわからなかった。
コンコン・・・
「梓、入るわよ。」
私はあえて返事はしない。
お母さんはそれがいつもの事だとわかっていて、ドアを開けた。
「今日も学校は行かないの?」
「・・・。」
「わかったわ。じゃあね・・・。」
これも毎朝繰り返す会話。
私が何も話さないのをわかっていて、お母さんは毎日欠かさずにやってくるのだ。
その後、お母さんは仕事に出かける。
これで家には私1人になり、ようやく音が消えて何故だかわからないが、とても安心できるのだ。
「朝ごはん・・・食べよう。」
独り言を呟きながら、冷蔵庫を開けて見渡すが、どうも食欲が湧かなかった。
結局今日もシリアルに少しだけ牛乳をかけたものを、もそもそと食べる私・・・。
あぁ、なんて情けない奴・・・。
私の中の小さなコップに水がとめどなく溢れ出た。
最近は頻繁に泣いてしまうせいか、目元が乾燥していた。
それを潤わせるような少しずつ少しずつ・・・。
こうして私は自分を保っているのだった。
雨がうるさい。
耳の鼓膜を突き破って、頭に刺さりそうだ。
ベットにあがって、少し高い窓辺に腰をかけ、片足はだらんと下に降ろし、ぼーっと外を見つめる。
何もしていない、考えていないのに溢れてくる涙。
それがどういう感情からなのかも私にはわからなかった。
コンコン・・・
「梓、入るわよ。」
私はあえて返事はしない。
お母さんはそれがいつもの事だとわかっていて、ドアを開けた。
「今日も学校は行かないの?」
「・・・。」
「わかったわ。じゃあね・・・。」
これも毎朝繰り返す会話。
私が何も話さないのをわかっていて、お母さんは毎日欠かさずにやってくるのだ。
その後、お母さんは仕事に出かける。
これで家には私1人になり、ようやく音が消えて何故だかわからないが、とても安心できるのだ。
「朝ごはん・・・食べよう。」
独り言を呟きながら、冷蔵庫を開けて見渡すが、どうも食欲が湧かなかった。
結局今日もシリアルに少しだけ牛乳をかけたものを、もそもそと食べる私・・・。
あぁ、なんて情けない奴・・・。
私の中の小さなコップに水がとめどなく溢れ出た。
最近は頻繁に泣いてしまうせいか、目元が乾燥していた。
それを潤わせるような少しずつ少しずつ・・・。
こうして私は自分を保っているのだった。