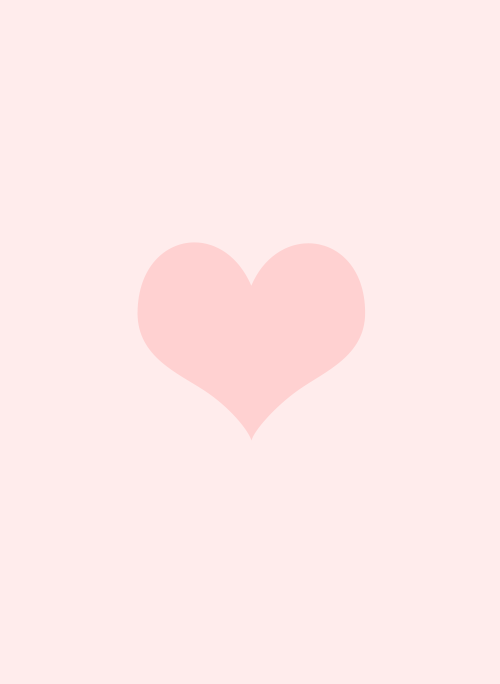たどり着いた駅で、わたしは改札の前で彼に向かって深々と頭を下げた。
「あの、ご迷惑かけて本当にすみません。ありがとうございました」
「いやいや、気ぃつけてね」
気にしないでとでも言うように、彼はひらひらと手を振ってみせた。
わたしは意を決して、ぎゅっとシフォンスカートを握りしめる。
緊張で、手のひらが汗ばんできているような気がした。
「……えっと、あの、お名前、は……?」
「俺? 長谷川 奏佑(はせがわ そうすけ)」
今さら名前を訊ねたわたしに気分を害した様子も見せず、いたってあっさりと答える。
じゃあね、と片手を挙げて、彼はもといたカラオケボックスへと戻って行った。
……たしか、今日の相手の男の子たちは、全員ひとつ年上だ。
それであの人、同じ学校だって、言ってた。
「……そうすけ、先輩……」
ぽつりと、自然に彼の名前が口から漏れる。
それだけでもう、まるで新しい宝物を見つけたときのように、胸がドキドキ高鳴った。
──16歳の、夏の終わりかけ。
わたしは生まれて初めて、『恋』という感情を覚えた。
「あの、ご迷惑かけて本当にすみません。ありがとうございました」
「いやいや、気ぃつけてね」
気にしないでとでも言うように、彼はひらひらと手を振ってみせた。
わたしは意を決して、ぎゅっとシフォンスカートを握りしめる。
緊張で、手のひらが汗ばんできているような気がした。
「……えっと、あの、お名前、は……?」
「俺? 長谷川 奏佑(はせがわ そうすけ)」
今さら名前を訊ねたわたしに気分を害した様子も見せず、いたってあっさりと答える。
じゃあね、と片手を挙げて、彼はもといたカラオケボックスへと戻って行った。
……たしか、今日の相手の男の子たちは、全員ひとつ年上だ。
それであの人、同じ学校だって、言ってた。
「……そうすけ、先輩……」
ぽつりと、自然に彼の名前が口から漏れる。
それだけでもう、まるで新しい宝物を見つけたときのように、胸がドキドキ高鳴った。
──16歳の、夏の終わりかけ。
わたしは生まれて初めて、『恋』という感情を覚えた。