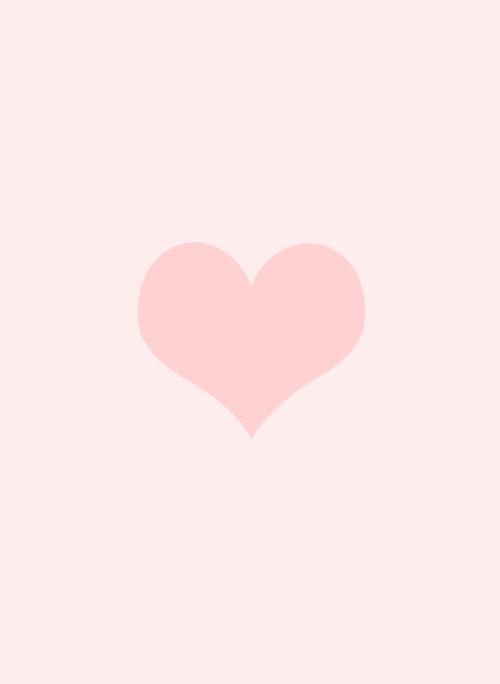「……傘、持っていけよ」
小さく音をたてて、ドアが閉まる。
とたんに足の力が抜けて、私はぺたりとその場に座り込んだ。
「はあ……」
詰めていた息を吐くと、やっと時が動いたように感じる。
驚いた、なんて言葉だけじゃ、とても言い表せられない。
本当に、心臓が止まるかと思った。
カーっと頬が熱くなって、涙までにじんでくる。
「……キス、されるかと思った……」
思わずそう口に出してから、また、体温が上がったような気がした。
震える両手のひらで、熱さを確かめるように自分の頬を包む。
──あそこで、辻くんがやめなかったら。今ごろ、どうなってしまっていたんだろう。
きっと胸のドキドキは、こんなものじゃ済まなかったに違いない。
『わかってない。俺がいつもどんな気持ちで、おまえのこと見てるのか』
すっぽりと、囲われてしまった。彼の腕や、胸板や、空気に。
自分の小さい体なんて、ひ弱でちっぽけなものだった。
……いつかの、テニスボールから庇ってもらったとき。
部活のユニフォームを着ていた、あのときとはまるで違う。
『……抵抗すんなら、もっとちゃんとしてくれよ』
低く響く声。熱っぽい瞳。
湿った濃い雨の匂いに混じって、知らない男の子の、匂いがした。
小さく音をたてて、ドアが閉まる。
とたんに足の力が抜けて、私はぺたりとその場に座り込んだ。
「はあ……」
詰めていた息を吐くと、やっと時が動いたように感じる。
驚いた、なんて言葉だけじゃ、とても言い表せられない。
本当に、心臓が止まるかと思った。
カーっと頬が熱くなって、涙までにじんでくる。
「……キス、されるかと思った……」
思わずそう口に出してから、また、体温が上がったような気がした。
震える両手のひらで、熱さを確かめるように自分の頬を包む。
──あそこで、辻くんがやめなかったら。今ごろ、どうなってしまっていたんだろう。
きっと胸のドキドキは、こんなものじゃ済まなかったに違いない。
『わかってない。俺がいつもどんな気持ちで、おまえのこと見てるのか』
すっぽりと、囲われてしまった。彼の腕や、胸板や、空気に。
自分の小さい体なんて、ひ弱でちっぽけなものだった。
……いつかの、テニスボールから庇ってもらったとき。
部活のユニフォームを着ていた、あのときとはまるで違う。
『……抵抗すんなら、もっとちゃんとしてくれよ』
低く響く声。熱っぽい瞳。
湿った濃い雨の匂いに混じって、知らない男の子の、匂いがした。