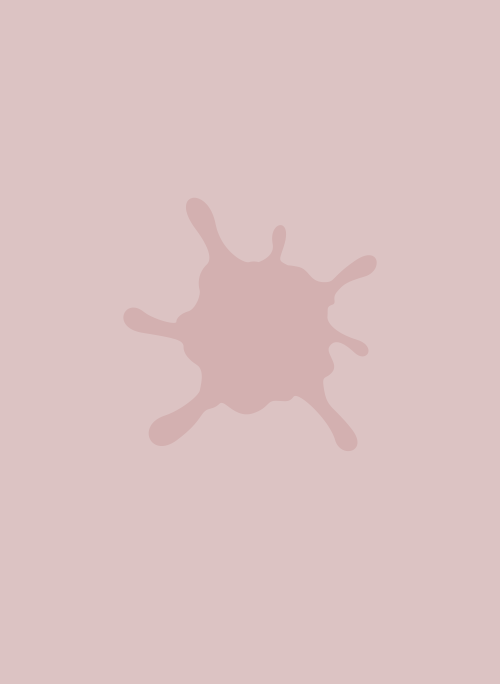だが、俺に傷付いて萎えている権利などない。とにかく一刻も早く千恵の所まで向かうのが先決だった。
千恵の家は俺の家より学校側の方だ。元々俺の家は学校からは離れているが、千恵の家は幸いなことにあまり距離がない。
ものの十数分で千恵の家に到着したが、息は荒れて、体力はもう既に限界に達していた。
だがそこで立ち尽くすわけでもなく、千恵の家のドアにぶつかるように身体を預けながら、家のインターホンを押した。
中でインターホンの音は薄々聞こえるが、誰も来ない。さっき家に入る前はどこも電気が付いていないので、少なくとも親は居ないのは確かだった。
俺はもう一度インターホンを押してみるが、誰もくる様子はない。荒れている息を止めて、耳をドアに押し付けて中に誰かいるか確認してみた。
すると少しだけ音が聞こえてくる。それは音自体は小さいが、何が倒れたり、誰かの叫び声のように感じた。
「!お、おい!千恵!千恵!?」
俺はドアをドンドンと叩いて呼び掛けるが変化はない。ダメもとでドアノブを引いて無理矢理開けようとしたら、思ったより簡単に開いて、その勢いで尻もちを着いてしまう。いや、元々開いていたらしい。
ズキズキと痛む尻を抑えながら靴はちゃんと脱いで家に入った。