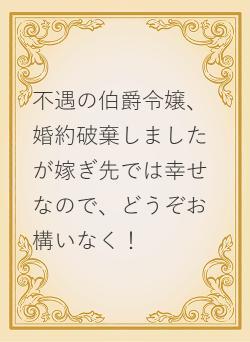俺の目の前には見た事ない程に冷えた瞳で、そして感情の見えない表情で森口を見つめる夏美がいた。
その夏美から出てくる言葉たちは夏美の叫びだと思うのに、その声音は平坦そのもの。
どこまでも欠落していく感情で言われる言葉達にその場に居た俺とサチ、それを向けられた森口も遮られたあとは何も、言い返すことが出来なかった…。
そして、夏美は平坦な声と無表情に冷えた瞳のまま家を出てしまった。
あまりの事に身動き出来なかった。
時間にしてほんの数分の出来事なのに。
ハッとして我に返ってから、俺は慌てて家を出た夏美を追いかけた。
あんな状態の夏美を一人になんてしたくない。
させたくない。
掴まないと、捕まえないと…。
そうして駆け出したものの、どこに行くのか検討もつかない。
だからとりあえず最寄り駅に向かって走る。
やっとその背中を見つけた時、夏美はタクシーに乗り込む所だった。
「夏美!!!」
力の限り、大声で叫んでもどうにもならない距離。
夏美の乗り込んだタクシーは、俺が追いつくこともままならぬうちに走り出してしまった。
目の前で離れていったその光景から途端に襲ってくるのは、夏美を失う恐怖。
もうここには帰ってこないのではないかという、したくもない最悪の事態を予測して俺は立ち尽くした。
そこにあとから追い付いてきたサチが俺に声を掛けてくる。
「アカリ、夏美は?!」
「タクシーに乗って行った。間に合わなかった…」
「とりあえず、一旦戻りましょう。森口は帰したから…」
そうサチに言われて落胆を隠しきれないままに自宅に戻る。
戻ったそこには冷えてしまったが夏美が作ってくれてた料理がきちんとテーブルに並んでいた。
サチと夏美、俺の三人分。
いつもならここで温かいまま賑やかに三人で食事していただろうに…。
ここに、肝心要の夏美がいない。
サチと二人のときは大した会話もなく、食べながらするのも仕事の話。
和やかに温かい食卓になり、家の中が柔らかく居心地良くなったのは夏美が来てからだった。
「暗いわね…。夏美は我が家の太陽だから…」
そう零しながら、サチもダイニングの料理を見つめていた。